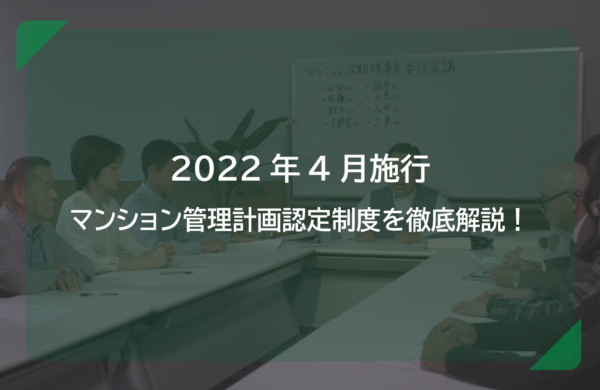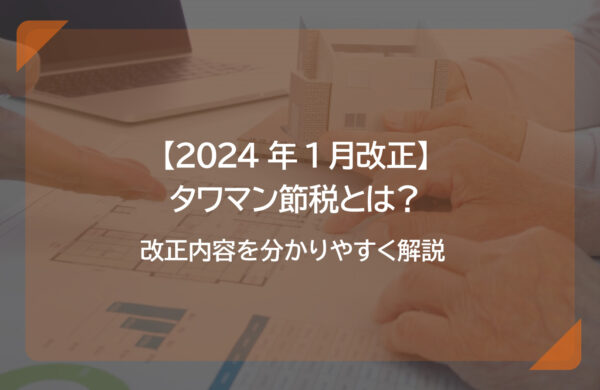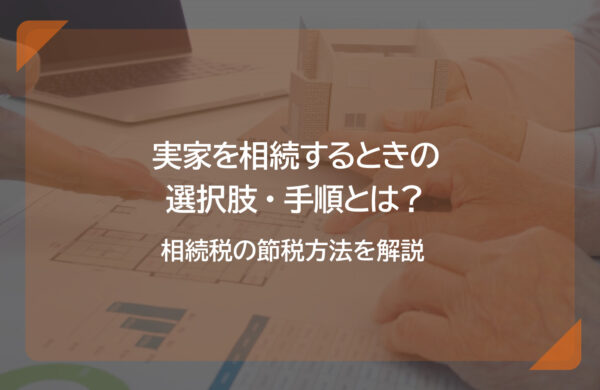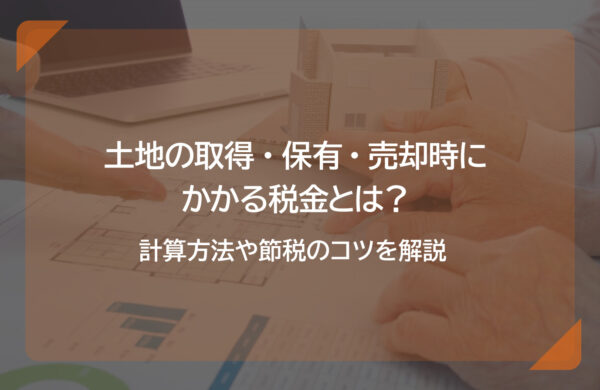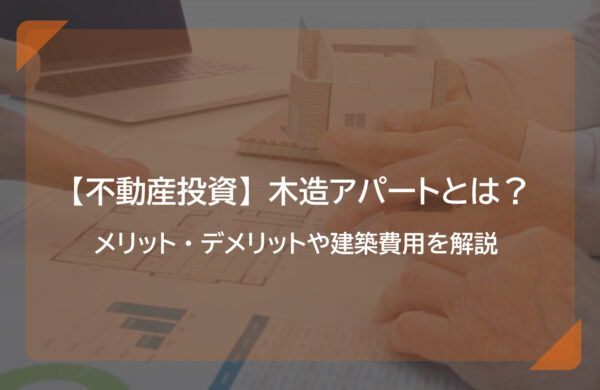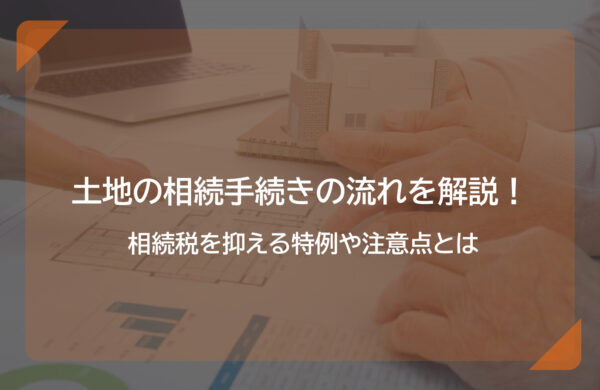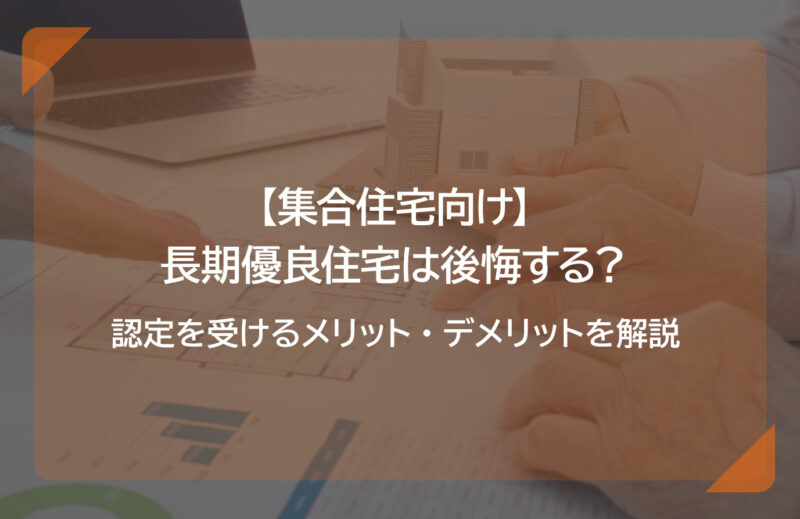
長期優良住宅は次世代も含めて長く住み続けられる住宅として、実需物件・収益物件ともにさまざまなメリットがあります。ただし、認定を受けるためには一定の基準をクリアしなければならないなどいくつかデメリットもあります。この記事では、長期優良住宅の認定を受けるメリット・デメリット、認定基準の詳細や認定を受ける手順、長期優良住宅の注意点などを解説します。
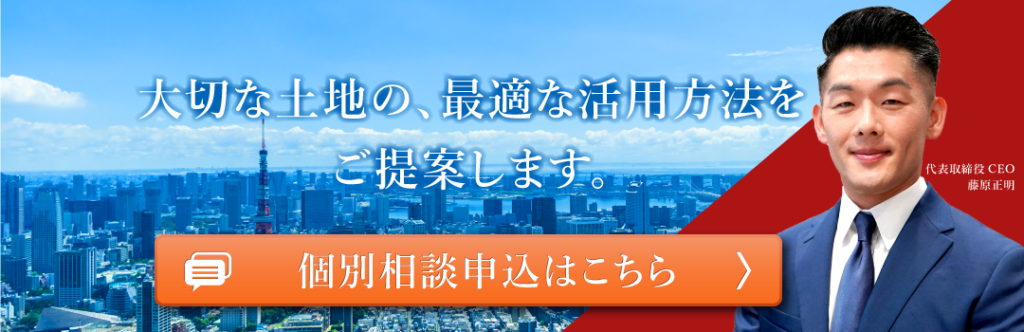

目次
そもそも長期優良住宅とは何か
長期優良住宅とは、国土交通省が推進している認定制度を受けた住宅のことです。住生活の向上や環境への負荷軽減を目的としており、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」と定義されています。戸建て住宅はもちろん、共同住宅も対象です。また、新築だけではなく、増築・改築時も認定を受けられます。
長期優良住宅の認定制度は新築に対するものが2009年から、増築・改築の対象は2016年から始まりました。認定を受けるためには、さまざまな基準をクリアしなければなりません。例えば耐震等級2級以上の強度があるなど耐震性の強さ、省エネルギー性、バリアフリー性などです。
認定基準については、詳しく後述します。
長期優良住宅のメリットをわかりやすく解説
長期優良住宅の認定を受けると、どのようなメリットがあるのでしょうか。具体的には以下の3つのメリットがあります。
メリット1:入居者へのアピールになる
長期優良住宅は、長期間住み続けることを前提として建てられています。認定基準には耐震性の項目もあり、建物の耐震等級がランクアップすることにより、地震に対する安心感を入居者に与えられるのは大きなメリットです。
長期優良住宅の認定基準には省エネルギー性などの項目もあるため、環境意識が高い人や環境負荷を考慮する人には好まれるでしょう。長期優良住宅は断熱性能など省エネルギー性能が高いため、冷暖房費の節約ができます。
長期優良住宅のメリットをアピールすることで、質の高い住生活を求める入居者への物件訴求力となるのです。
メリット2:補助金を利用できる
長期優良住宅は政府が推進していることもあり、補助金を受けられることもメリットです。補助金を受けるためには要件を満たしている必要がありますが、補助金を活用できれば建築費用・改築費用の節約につながります。
例えば2015年から始まった「地域型住宅グリーン化事業」は、省エネルギー性や耐久性に優れた木造住宅の整備に対する補助金です。地域型グリーン化事業の補助金は、国土交通省の採択を受けた中小工務店で木造住宅を建築するのが要件で、共同住宅の場合、最大140万円×戸数の補助を受け取れます。
メリット3:税金の優遇を受けられる
長期優良住宅は、税金面でさまざまな優遇を受けられるのも大きなメリットです。不動産取得税、固定資産税の2種類で軽減されるメリットがあります。各税金の詳細を見てみましょう。
税金の優遇1:不動産取得税
不動産取得税は、土地・建物の不動産を取得した際に課税される都道府県税です。一般的な住宅の不動産取得税は「(固定資産税評価額-1,200万円)×戸数×3%」で計算されます。一方で、長期優良住宅の場合は控除額が1,300万円に拡大されており、「(固定資産税評価額-1,300万円)×3%」です。
不動産取得税の軽減措置には面積要件があります。収益物件の場合、1戸あたりの床面積が40m²〜240m²であることが必要です。
税金の優遇2:固定資産税
固定資産税も2024年4月時点で、2026年3月31日までに新築された住宅を対象として減税されています。一般的な戸建て住宅を新築した場合、固定資産税は3年間2分の1に軽減される期間が設けられています。それが長期優良住宅を建てた場合は、2分の1に減額される期間が5年に延長されます。
マンションなど3階以上の中高層耐火住宅を建築したケースでは、2分の1に軽減される期間が一般的な建物で5年間であるところ、7年間に延長されます。適用を受けられる面積要件は、収益物件の場合40m²〜280m²です。
メリット4:地震保険料が割引される
地震保険の保険料は住宅の耐震等級をもとに割引率が決まる仕組みになっているため、一定の耐震性を認められている長期優良住宅は地震保険料の割引が適用される基準をクリアしています。割引を受けるためには、所定の書類を保険会社に提出する必要があります。地震保険の割引制度は以下通りです。
| 割引名 | 割引率 | |
| 免震建築物割引 | 50% | |
| 耐震等級割引 | 耐震等級3 | 50% |
| 耐震等級2 | 30% | |
| 耐震等級1 | 10% | |
| 耐震診断割引 | 10% | |
| 建築年割引 | 10% | |
ただし、長期優良住宅で割引の対象になるのは地震保険料の部分のみで、火災保険料は割引の対象外になっていないるため、注意してください。
火災保険には、「新築割引」「オール電化住宅割引」等がありますので、保険会社に確認してみましょう。
メリット5:空室対策として有効
長期優良住宅の認定を受けている物件は、快適に長い期間住み続けられるという一般的な住宅にはない特徴を持つことになります。特に耐震性を重視する人や、環境負荷が抑えられた住宅に興味がある人などには選ばれる可能性が高いでしょう。
省エネルギー性の高い物件の場合は、夏の暑さや冬の寒さにも強く、室内環境が快適です。長期優良住宅はほかにも維持管理や災害配慮などさまざま認定基準をクリアしているため、入居希望者へのアピールポイントになります。
長期優良住宅を建設するデメリットとは
長期優良住宅にはここまで解説してきたようなメリットがあるものの、いくつかデメリットもあります。長期優良住宅の建設にあたっては、以下の4点に注意してください。
デメリット1:時間がかかる
長期優良住宅の認定を受けるためには申請手続きを行わなければならず、申請後も認定を受けるまでに時間がかかります。長期優良住宅の建築は長期優良住宅の認定が下りてからしかスタートできないため、通常の住宅と比較して着工自体が1週間から1か月ほど遅れる場合があります。
性能の高い住宅の建築は、工期も長くなりがちです。アパートやマンションなどの賃貸物件の場合、引っ越しシーズンに合わせて完成させたいことが多いでしょう。入居者を逃さないためには、スケジュールに余裕を持って建築の計画を立てる必要があります。
デメリット2:建築コストがかさむ
長期優良住宅の認定を受けるためには、構造や設備、仕様などの基準をクリアしなければなりません。耐震性や省エネルギー性をはじめ、さまざまな基準を満たそうとすると、それだけ建築コストが高くなる可能性があります。
長期優良住宅の普及が進んでいるため、標準で長期優良住宅の認定をクリアできる施工会社も増えてきました。ただ、一般住宅と比較すると建築コストがかさむことも考えられるため、建築の予算計画はしっかりと立てるようにしましょう。
デメリット3:申請にお金がかかる
長期優良住宅の認定を受けるためには、所管行政庁に申請をしなければなりません。その申請にも、費用が発生します。審査や認定に関する手数料の金額は、地域によって異なりますが、おおむね5~6万円ほどです。
ただし、自分で申請手続きを行うためには、認定申請書の作成やはもちろん、設計内容説明書や各種図面・計算書などの添付書類をそろえるのに時間も手間もかかります。申請手続きは施工会社・工務店に代行してもらうことも可能です。
デメリット4:定期点検が必要
長期優良住宅の認定基準には、維持保全計画という項目があります。長期優良住宅は次世代まで住み続けられるほど、長期間性能が落ちないような住宅でなければなりません。そのため、建築時だけではなく、建築後の維持管理も認定基準に入っているのです。
認定基準をクリアするためには、住宅の完成後も定期点検を行う必要があります。万一、維持保全が疎かになっていると判断されると、認定が取り消される場合もあるため注意してください。
長期優良住宅には認定基準がある
長期優良住宅の認定を受けるためには、基準を満たしていなければなりません。以下で認定基準の10項目を解説します。
長期優良住宅の認定基準:劣化対策
数世代にわたって住める構造躯体を備えていることが認定基準です。具体的には劣化対策等級3かつ、構造によってさらに細かく基準が設けられています。例えば、木造では床下空間の有効高さ確保や小屋裏の点検口設置などです。鉄骨造ならば鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置、鉄筋コンクリート造ならば水セメント比率を減ずる、またはかぶり厚さを増すなどの基準があります。
長期優良住宅の認定基準:耐震性
大地震が発生しても利用し続けられるよう、強度を高めていることが求められます。いくつか基準が設けられており、品確法に定める免震建築物であることがそのひとつです。また、耐震等級2であること、2階以下の木造建築物等で壁量計算による場合にあっては耐震等級3であることなど、基準のいずれかに該当している必要があります。
長期優良住宅の認定基準:省エネルギー性
長期優良住宅では断熱性能など、省エネルギー性能を備えていることも求められます。具体的には断熱等性能等級5かつ、一次エネルギー消費量等級6をクリアしていなければなりません。上記の劣化対策や耐震性も同様ですが、省エネルギー性についても戸建て住宅・共同住宅のどちらも、この基準を満たしている必要があります。
長期優良住宅の認定基準:維持管理・更新の容易性
維持管理・更新の容易性とは、補修やリフォームがしやすいことです。特に構造躯体に比べて配管設備などは耐用年数が短いため、認定基準として設けられています。専用配管の維持管理対策等級は、一戸建て住宅も共同住宅も等級3が必要です。共同住宅に関しては、共用配管の維持管理対策等級3、共用配水管の更新対策も等級3をクリアしていなければなりません。
長期優良住宅の認定基準:可変性
時間が経過すると、居住者のライフスタイルに変化が生じることも考えられます。そのため、間取りの変更がしやすいような措置が講じられているかどうかが基準となっています。可変性に関する認定基準が設けられているのは共同住宅と長屋のみで、戸建て住宅には課されていません。具体的な基準は、躯体天井の高さが2,650mm以上です。
長期優良住宅の認定基準:バリアフリー性
可変性と同じく、居住者のライフスタイルが変化しても対応できるよう、共同住宅の新築時に課せられている認定基準です。将来バリアフリーを考慮に入れた改修がしやすいスペースを確保しているかどうかが、基準になっています。具体的には高齢者等配慮対策等級(共用部分)で、等級3をクリアしていることが要件になっています。
長期優良住宅の認定基準:居住環境
長期優良住宅には、居住環境に配慮することも求められています。良好な景観の形成や地域の居住環境の維持・向上に配慮された建物であることが要件です。地域によって地区計画や景観協定など、さまざまな定めが設けられていることがあるため、計画や協定などの内容と調和を図った建物を建築する必要があります。居住環境に関する認定基準は、戸建て住宅と共同住宅のどちらも対象です。
長期優良住宅の認定基準:住戸面積
長期間快適に暮らしていくためには、良好な居住水準を確保できるだけの面積が必要です。一戸建て住宅は75m²以上(少なくとも1階の床面積が40m²以上)、共同住宅が40m²以上の面積を有している必要があります。2022年の法改正以前は共同住宅の基準が55m²でしたが、改正後は40m²になったことで、基準をクリアしやすくなりました。
長期優良住宅の認定基準:維持保全計画
長期優良住宅は、そもそも長く住み続けることが前提です。そのため、将来を見すえた維持保全計画も認定基準となっています。住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分、給水または排水のための設備について、定期的な点検・補修に関する計画が策定されていることが要件です。もちろん計画を作るだけではなく、必要な時期に点検を実施する必要もあります。
長期優良住宅の認定基準:災害配慮
改正前の認定基準でも地震に対する耐震性は設けられていたものの、地震以外の災害リスクには対応していませんでした。そこで2022年の法改正では、災害に関する認定基準が追加されています。災害発生のリスクのある地域においては、リスクの高さに応じて被害の発生防止や軽減に配慮した措置を講じることが求められるようになりました。
長期優良住宅の認定を受ける手順を解説
ここからは、具体的に長期優良住宅の認定を受けるためにはどうすればいいのか、手順を追って解説していきます。
手順1:認定条件を満たす設計を検討する
長期優良住宅の認定を受けるためには、なによりも認定条件を満たす設計でなくてはなりません。共同住宅を建設する場合の認定基準は以下の10項目あり、すべてをクリアしている必要があります。
・劣化対策
・耐震性
・省エネルギー性
・維持管理・更新の容易性
・可変性
・バリアフリー性
・居住環境
・住戸面積
・維持保全計画
・災害配慮
手順2:技術審査を受ける
長期優良住宅の認定申請を行う前に、確認申請書または設計住宅性能評価申請書、添付図書を添えて登録住宅性能評価機関の技術審査を受ける必要があります。登録住宅性能評価機関は、日本住宅性能表示基準の性能について客観的に評価を行う機関です。基準をクリアすると、適合証が交付されます。
手順3:認定申請を出す
技術審査で適合証が得られたら、所管行政庁に認定申請を出します。申請時に必要な書類は、認定申請書と確認書等や各種図面、その他所管行政庁が必要と認める書類などの添付図書です。同時に建築確認審査を希望する場合は、建築確認に関する申請図書も添付してください。適合審査の結果、認定されると認定通知書が交付されます。
長期優良住宅にすべきか検討する際のポイント
アパートやマンションなどの共同住宅の場合、長期優良住宅に対応していると長期間運用できるのもメリットになるでしょう。ただし、建築コストが高くなると、利回りは低めになってしまう可能性もあります。
長期優良住宅の認定基準をクリアする住宅を建築するためには、耐震性や省エネルギー性をはじめ、さまざまな技術が必要です。長期優良住宅の建築に実績があり、希望に沿う建物を建ててくれる施工会社や工務店があるかどうかなど、依頼先の選定もポイントになるでしょう。
長期優良住宅を建設するときの注意点とは
長期優良住宅にはメリットだけではなくデメリットもあるため、実際に建設を検討する際は以下の注意点を踏まえておいてください。
絶税額と建築コストを比較する
長期優良住宅は補助金を活用できたり、各種税金の控除や地震保険料の割引が受けられたりなど、さまざまなメリットがあるものの、建築にかかるコスト自体は割高です。節税や割引が受けられても、建築コストが高すぎると、結局予算オーバーになってしまうこともあり得ます。長期優良住宅を建てるメリットが大きいかどうか、節税できる金額と建築コストを慎重に比較してください。
まとめ
長期優良住宅は認定基準をクリアしなければ建てられませんが、その分、耐震性や省エネルギー性、バリアフリー性などに優れています。しかも長期間快適に住み続けられる安心感を得られるのは、長期優良住宅の大きなメリットです。
安心して生活できるメリットは、そのまま入居者へのアピールにもなります。建築にあたって税金の優遇が受けられたり、地震保険料が割引されたりなど、コスト面でもメリットがあるでしょう。
大和財託では劣化対策等級3を取得した物件を標準で建てています。希望であれば、他の項目も満たした長期優良住宅仕様の住宅を建築することも可能です。建てて終わりではなく、長期的な資産運用までサポートを行い、投資対効果の高いリフォーム・修繕工事も行っています。長期優良住宅も選択肢に入れつつ、土地活用を検討しているのなら、当社の「個別相談」までご相談ください。
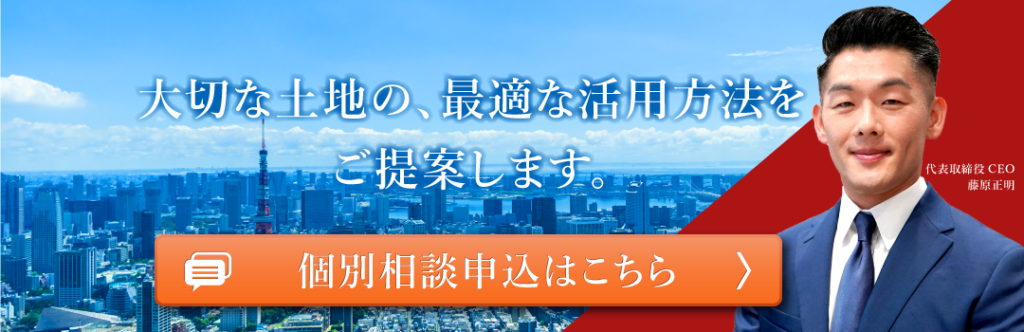

監修者

藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO
昭和55年生まれ 岩手県出身
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発業務に携わり、その後関東圏の不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
平成25年に大和財託株式会社を設立。不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を東京・大阪をはじめとする主要都市圏で展開する。
資産価値を創る様々なサービスを駆使し、“圧倒的顧客ファースト”を掲げ、お客様の人生に伴走しながら今までにない価値を開発・建築している。
自社で運営しているYouTubeチャンネル『藤原正明の「最強の不動産投資チャンネル」<大和財託株式会社>』やXといった様々なプラットフォームで資産運用についての知識や考え方を発信している。
書籍「収益性と節税を最大化させる不動産投資の成功法則」や「収益性と相続税対策を両立する土地活用の成功法則」を発売中。