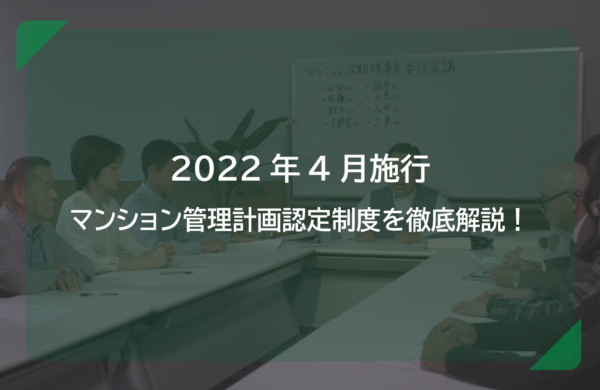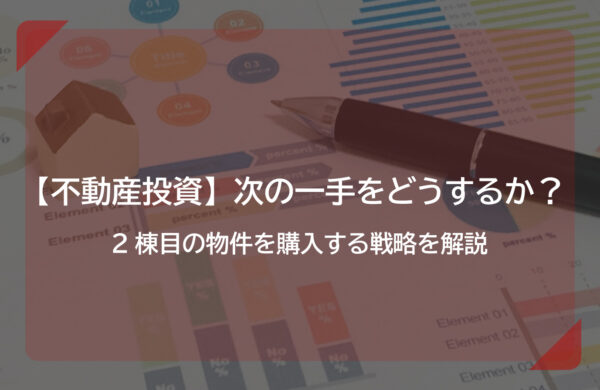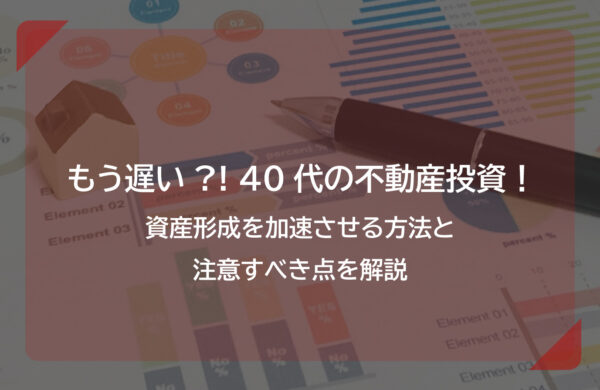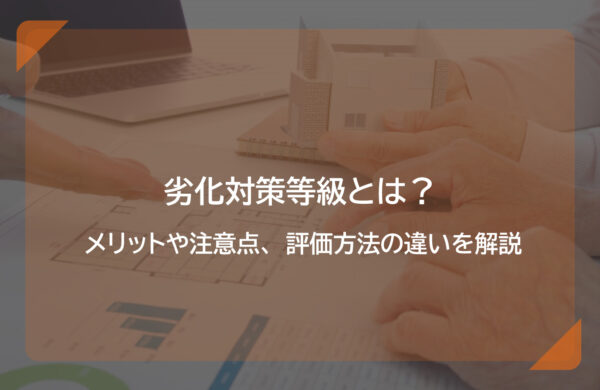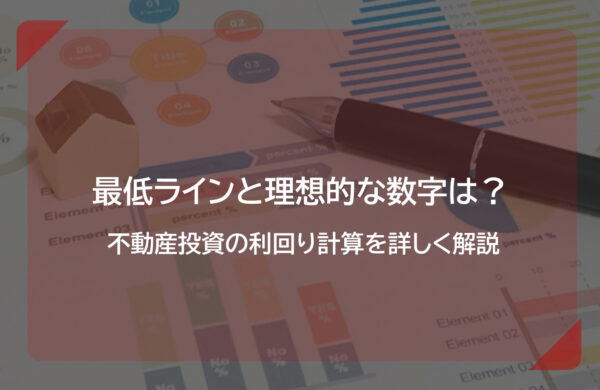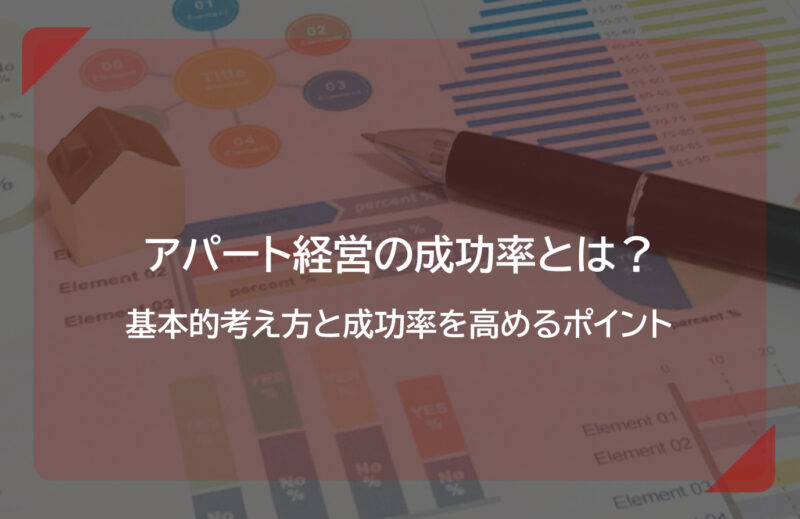
アパート経営が副収入や年金代わりになるという話はよく聞きます。しかし、不動産投資の経験がないと、アパート経営が本当に成功するのか、落とし穴はないのか心配に思う人も多いでしょう。
アパート経営で失敗しないためにはセオリーがあり、成功率を高めるポイントを押さえることが重要です。この記事では、アパート経営の成功率はどれくらいで、アパート経営の成功とは何か、アパート経営の基本的な考え方やアパート経営のメリット、開始の流れ、成功率を上げるポイントを解説します。
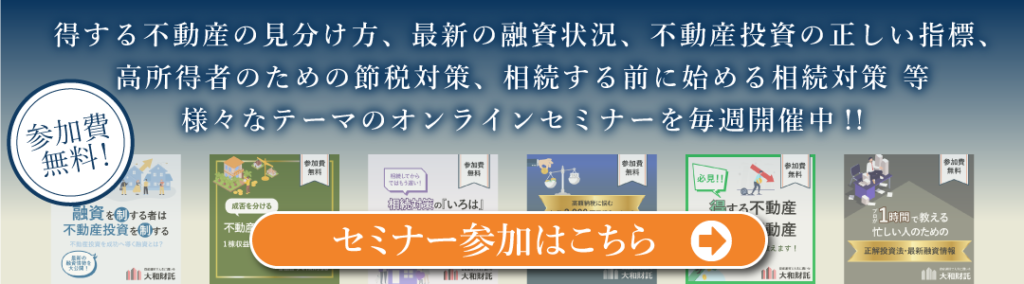
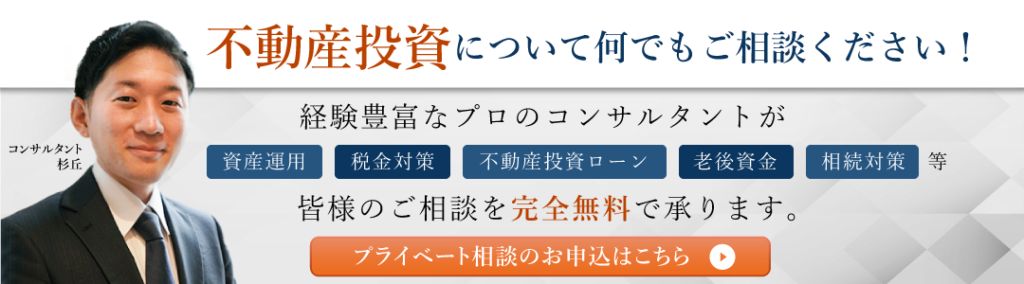
目次
アパート経営者の収入は
アパート経営者に限定した収入の統計情報は出ていませんが、参考として国税庁の「申告所得税標本調査結果」から、不動産所得の平均額を見てみましょう。
不動産所得者の所得平均額
- 2016年度:512万638円
- 2017年度:517万151円
- 2018年度:518万1,407円
- 2019年度:520万7,633円
- 2020年度:539万9,575円
出典:国税庁 申告所得税標本調査結果
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/shinkokuhyohon/toukei.htm#kekka
2016年から2020年まで500万円代前半で推移しています。収入所得の分布では、「300万円超400万円以下」が13.66%ともっとも割合が多く、次に「400万円超500万円以下」の10.44%が続いています。
上記の額は平均額なので、ある程度高額な不動産収入を得ている方が数値を引き上げている可能性がありますが、約4分の1にあたる24.1%の方が300万円から500万円の間に収まっている状況にあります。
また、2016年から2020年に向かって所得平均額は緩やかに上昇しています。2016年と2020年を比較すると、約5%増加しています。
2つのステージから見るアパート経営の成功
アパート経営が成功したと判断できるタイミングはどこでしょうか。安定したキャッシュフローを実現した段階と考える人が多いのですが、時期尚早です。アパート経営の真の成功は、フローに加えてストックの形成にも成功したタイミングといえます。
フローとストック、2つのフェーズに分けて解説します。
フローの形成期
フローとは、アパート経営で得た家賃収入から融資返済額と経費、税金を差し引いた、手元に残るお金のことです。フローの額が大幅にプラスであれば、現状は事業として健全であると考えられます。そのため、この段階で成功したと考える人が多くいます。
問題は、フローがプラスの状態を長年にわたって維持し続けられるかどうかです。アパート経営には空室や滞納、競合の参入などで稼働率が下がるリスクがあることに加え、建物・設備の修繕や老朽化にともなうリフォームなど、さまざまなところにフローを悪化させる可能性が潜んでいます。
フローが悪化しても、融資の返済は止められないので、返済原資の不足分を自分で補う手出しが発生する恐れがあります。物件を売却してアパート経営をやめる選択肢もありえますが、物件の売却額が融資残高を下回る状態になるとさらに大きな損失となるでしょう。
プラスのフローを実現しても、負債と純資産の状態を見ないと真の安定とはいえません。真の成功とは何か、次の「ストックの形成期」で見ていきましょう。
ストックの形成期
ストックとは、アパート経営で得た資産のことです。ストックの形成で大切なのは、貸借対照表の純資産を増やしていくことです。純資産が積み上がっていれば、いつでも手出しなしでアパート経営をやめられます。
例えば、物件価値2億5,000万円のアパートを10年間経営した場合を考えてみましょう。ここでは分かりやすいように自己資金は0円とし、年間に得られる賃料合計額は一定とします。金利は元利均等方式、融資期間は30年間とします。
物件金額:2億5,000万円
借入金額:2億5,000万円
年間賃料合計額:2,000万円
年間融資返済額:1,100万円
年間税引前キャッシュフロー:500万円
※ke!san ローン返済(毎月払い)
https://keisan.casio.jp/exec/system/1256183644
アパート経営開始時の貸借対照表
| 資産の部 | 負債の部 |
| 物件市場価値 2億5,000万円 | 借入残高 2億5,000万円 |
| 純資産 | |
| 0万円 |
アパート経営開始時はフローの積み上げがないので、物件市場価値がそのまま資産額になります。負債の部は返済が進んでいないので2億5,000万円全額。純資産は「資産の部」=「負債の部」の状態なので0万円です。
10年後の貸借対照表
| 資産の部 | 負債の部 |
| 物件市場価値 2億2,500万円 キャッシュフロー | 借入残高 1億4,000万円 |
| 純資産 | |
| 1億3,500万円 |
10年経つと物件市場価値が経年により2,500万円下落したものの、フローが10年間で5,000万円積み上がり、借入残高を1億51,000万円減らせたので、差額の1億3,500万円が純資産となりました。
この状態では、仮にアパートを売却したとしても純資産相当額の1億3,500万円を受け取れる計算(不動産譲渡税を省略)となるので、ひとまずアパート経営に成功したといえます。
アパート経営7つのメリット
アパート経営がほかの投資と大きく違う点は、「物件」という現物があることです。物件の運営という「事業」の形態をとるので、ほかの投資にはないさまざまなメリットを享受できます。ここでは、代表的な7つのメリットを紹介します。
1.安定的な家賃収入が期待できる
アパート経営は住宅という生活の基盤を提供しているので、経済動向や景気動向に左右されにくい特徴があります。そのため、物件選びを間違えなければ、長期にわたって安定的な収益が期待できます。
コロナ禍のときにおいても、商業ビルやオフィスビルは空室の増加が問題になりましたが、賃貸住宅ではこのような問題はあまり起こりませんでした。
住居系物件は家賃が安定しているのも強みです。オフィスなどの事業系物件は、景気動向や社会状況によって賃料が上下に変動しますが、生活の基盤に根ざした賃貸住宅は、家賃の変動は少なく安定しています。この点が、アパート経営を安定させている大きな要因なのです。
2.借り入れによってレバレッジ効果がある
レバレッジ効果とは、自己資金を原資にして金融機関から融資を受けることで、自己資金の力を何倍にも膨らませることをいいます。レバレッジとは「てこ」の意味があり、少しの資金でより大きな資金を動かせるさまからこの言葉が付きました。
投資で金融機関から融資を受けられるのは不動産投資の特権です。不動産投資は不動産事業でもあるので、金融機関は事業性を担保に融資をします。不動産投資で受ける融資を長期間に設定することで、キャッシュフローを黒字にしつつ無理のない返済計画を立てられます。
レバレッジを効かせれば短期間で大きな収益を生むこともできます。得た資金を元手に新たな物件を買い進めれば、さらに収益は加速していきます。
3.インフレ対策になる
資産を現金や預貯金で持ち続ける人は多いのですが、インフレ下では現金や預金の価値の相対的減少を生んでしまいます。
現金で保管していても、資産が増えることはありません。預貯金で保管していても利息がインフレに追いつくことはないでしょう。その間にも物価は上昇していくので、手持ちのお金で買えるものは徐々に減っていきます。つまり、相対的にお金の価値が減っているわけです。
不動産は実物資産なので、その価値は物価と連動する傾向にあります。保有しているだけで資産価値が大きくなるので、インフレに対応できるのです。
ただし、すべての物件の価格が上昇するわけではありません。賃貸需要があるエリアの物件であること、一定以上の利回りを確保している物件であること、建物管理が適正にされている物件であることなどが求められます。
4.管理会社に委託できる
アパートを自主管理するには多くの手間がかかりますが、管理会社へ委託すれば面倒な管理業務から解放され、管理会社が持つアパート経営のノウハウを活かすことができます。
一般的に、アパートの管理にかかる手数料は家賃の5%前後が相場と言われています。例えば賃料10万円の部屋が10部屋ある場合、1室あたりの手数料は月額5,000円で、10戸合計では5万円になります。
管理費に含まれる内訳は、共用部分の点検、各部屋の入居者募集や賃貸借契約・更新、家賃の集金などです。内訳は業者によって変わる場合があるので、契約をする際はどこまで含まれるのか確認しましょう。
自主管理は管理費の節約にはなりますが、入居者を探す手間や家賃滞納の対応などを考えるとおすすめはできません。アパート経営は長い歴史を持つ投資方法です。管理会社には多くのノウハウが蓄積されているので、プロに任せてしまったほうが安心といえるでしょう。
5.生命保険代わりになる
金融機関から融資を受けてアパート経営を始める場合、不動産投資ローンに団体信用生命保険(団信)が付与されていることがあります。
団信とは、ローンの契約者が死亡した場合や高度障害を負った場合などにローン残高が0円になる保険です。生命保険会社が契約者に変わってローン残債を金融機関に支払います。団信の保険料は利息に含まれているものが多く、大きな負担とはなりません。
団信にはいくつか特約を付けることができ、死亡と高度障害に加えて、がんや3大疾病、8大疾病も保険金支払いの対象にできるものがあります。
6.所得税・住民税の節税になる
アパート経営が住民税・所得税の節税になるのは、不動産所得が帳簿上赤字になった場合に、赤字分をほかの所得と相殺できる損益通算が適用できるためです。アパート経営以外に給与所得や事業所得がある場合、アパート経営の赤字分でそれらの黒字分を圧縮できます。
例えば、給与所得が700万円ある場合において、不動産投資で300万円の赤字が出たとすると、損益通算をすれば課税所得額は400万円になります。
所得税は課税所得が高くなるほど税率が大きくなる累進課税制度なので、損益通算で課税所得額を減額できれば、税金を減らせるのです。
不動産投資には、年数の経過にともなって建物の価値が減少した分を経費に算入できる減価償却という仕組みがあります。実際にはキャッシュアウトせずに大きな経費を計上できる会計ルールなので、節税に有効に働きます。
7.相続対策ができる
アパートが相続税対策によく名が上がるのは、現金などの金融資産の相続評価額が時価100%であるのに対して、土地・建物の相続評価額が時価より低くなります。
なぜ不動産が金融資産よりも相続税評価額が低く算定されるのかといえば、すぐに時価が判明する金融資産と違って不動産は価値を算定するのに時間がかかるからです。相続発生時に不動産の価値がすぐに確定できないため、相続税が不公平にならないように不動産の相続是評価額は時価の6~7割程度になるように設定されているのです。
さらに、賃貸用不動産の場合、他人への貸し付けによって自分で自由に利用できない分価値が下がるとされています。アパートの土地は「貸家建付地」と呼ばれ、他人に土地や建物を貸している割合である「借地権割合」や「借家県割合」によって評価額が減額されます。借地権割合は状況に応じて30~90%で適用され、借家権割合は30%です。
アパート経営を始める流れ
ここからは、アパート経営を始めるまでの流れに沿ってポイントや注意点などを見ていきましょう。アパート経営ではふまえるべきポイントが存在しています。ポイントを間違えると、アパート経営に失敗する恐れがあります。
アパート経営の目標を決める
最初に決めるのはアパート経営の目標です。アパート経営の目標が老後資金の確保なのか、副収入の確保なのか、節税なのかによって投資戦略が変わってきます。
例えば、給与所得や事業所得が高くて所得税の納税額が高い場合、節税を目的としたアパート経営を目指すケースがあります。ここでは、節税に適した物件の取得や売却計画を立てる必要があります。
絶対にやってはいけないのは、見切り発車でアパート経営を始めて、あとから目標を決めることです。アパート経営は目標と投資戦略がかみ合ってこそ効果を発揮するものです。利回りなどの表面的なメリットだけにひかれて始めてしまうと、いかに好条件の物件でも良い結果が得られるとは限りません。投資戦略はあくまで目標達成のための方法と理解しましょう。
コンサルタントに相談する
アパート経営の目標が決まったら、コンサルタント、または不動産投資コンサル会社に相談しましょう。目標があいまいな場合は、目標設定も込みで相談してもよいでしょう。
当社・大和財託では、まず物件選定の前条件となる目標達成のための資金計画を作成します。資金計画で決める内容には以下のようなことがあります。
- 必要な取得資金
- 自己資金とローンの割合
- ローンの金利タイプや商品
- ローンの返済方法・返済期間
この段階はいわば、あなたの現状を正確に把握するステップです。無理のないアパート経営で目標を達成するために、可能な限り具体的な情報を提供しましょう。
物件を選定する
コンサルタントと目的や条件の共有ができたら、目標達成に適した物件を探します。まずは条件から探し、いくつか目星を付けたあとで、現地調査や物件内覧、レントロールなどの資料精査などを行います。
物件は資料や写真だけではわからない部分が多いので現地調査や物件内覧は念入りに行いましょう。あとから問題が発覚するとフローに影響を及ぼす可能性があります。
その後に収支計画のシミュレーションを念入りに行います。空室率や資産価値の減少幅などを考慮して、10年・20年単位の長期的な収支決算(フロー計算、損益計算)を作成し、同時に出口戦略も考えておきます。
アパート経営に出口戦略はとても重要です。ローン返済が完了しても資産として保有し続けるのか、途中で売却して新たな物件を購入するのかなど、出口戦略によってその次の方向性が変わってきます。
物件購入申し込みをする
物件を購入するときは、販売会社または仲介会社に「買付証明書」という書類を提出します。買付申込書とは、販売者に対して購入したい意図と条件を伝えるための書類です。一般的に記載する内容は下記のとおりです。
〈買付申込書に記載する事項〉
- 宛名(売主名)
- 購入希望者の住所・氏名
- 購入したい物件の情報(物件名、所在地、構造、面積など)
- 購入希望金額
- 手付金や中間金の有無や金額
- 売買契約日
- 支払い方法
- 買付申込書の有効期間
- 購入希望者の情報
- その他条件
買付申込書は法的に定められた書類ではないので、統一された書式はありません。
融資の事前審査を受ける
不動産投資ローンの「事前審査」とは、物件の売買契約を締結する前に融資を受けられる可能性を概ね判断してもらうことです。仮審査と呼ばれる場合もあります。
審査では、資産の状況や将来性、借入対象不動産の詳細や収益性などを確認します。審査に必要な書類は金融機関によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。
不動産投資ローンの審査に必要な書類
- 住民票の写し
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
- 所得が確認できる書類
- 金融資産が確認できる書類
- 借入状況が確認できる書類
- 借入対象不動産の資料
上記の書類に加えて、連帯債務者や連帯保証人についても1~6を用意します。
不動産売買契約を結ぶ
次に不動産売買契約の段階へと進みます。このとき、契約を締結したあとに融資の本審査に落ちる可能性を考え、融資が通らなかった場合に契約が解除となる「ローン特約」を必ず付けておきます。
また、「重要事項説明」はしっかり受けましょう。重要事項説明とは、売買契約を締結する前に物件の概要や各種条件を説明する手続きです。宅地建物取引業法に定められており、必ず宅地建物取引士が説明しなくてはいけません。説明する内容は物件の概要や法令に関する事項、建物や土地の形状、取引条件などです。
管理会社を選ぶ
購入した物件の管理を任せる管理会社を選びます。売主である不動産会社が管理会社を兼ねるケースもありますが即決せず、ほかの管理会社とも比較してから選びましょう。
管理会社を選ぶときの主なポイントには以下のようなことがあります。
- 管理手数料:家賃の5%前後を目安に検討する
- 管理実績:管理物件の入居率の高さ、管理戸数の多さ
- 管理体制:日常管理の体制、トラブル発生時の体制
- 空室対策:空室が発生した場合の具体的な対応策
- サービスの充実度・品質:サービス内容、管理会社で対応してくれる範囲
なお、管理手数料の安さだけで選んではいけません。本当に重視すべき点は、長期間にわたって管理を任せられるかどうかです。管理手数料が安くても、空室が多かったりトラブルが解消せずに解約されてしまったりすると、結果的に損をする可能性があります。
融資の本審査を受ける
金融機関に正式に融資の申し込みをして審査を受けます。審査が通ったら、金融機関と金銭消費貸借契約を結びます。
事前審査で融資見込み有りと判断されていれば、多くの場合審査に通ります。しかし、稀に本審査で審査落ちになる場合があります。また、融資額を減額する「減額承認」となる場合もあります。
本審査で落ちやすくなる理由には以下のようなものがあります。
- 事前審査と申告内容が違う
- 提出書類の誤りや不備
- 資産状況や物件状況の変化
- 審査項目の追加
なかでも申告内容や提出書類の誤り・不備は絶対に避けてください。正しい情報を伝えられないだけでなく、虚偽の情報を伝えたとして信頼を下げる可能性もあります
物件の引渡し
本審査に通って資金のめどが付いたら物件を引渡してもらいます。このとき行うべき主な内容は以下のとおりです。
- 物件の最終確認:設備や建物の状況などが契約どおりか再度確認する
- 融資の実行:金融機関の融資が実行される
- 残代金の決済:契約金額から手付金や申込金を差し引いた残金
- 所有権移転登記:所有権の移転が完了しているか確認する
- 物件の引渡し:物件の引き渡しを受ける
物件の最終確認は念入りに行いましょう。例えば、エアコンや給湯器の設置や動作は問題ないか、契約から引き渡しの間に新たな瑕疵(欠点や問題点)は発生していないかなどです。
融資の実行、残代金の決済、所有権移転登記、物件の引渡しは、原則として同日に行います。気持ちよくアパート経営を始めるためにも、細心の注意を払って引渡しに臨みましょう。
アパート経営の成功率を高めるポイント
アパート経営の成功率を高めるには、実際に始める前の下準備が大切です。むしろ始める前の準備で大部分が決まると言っても過言ではありません。
ここでは、アパート経営を始める前に特に注意すべき、4つのポイントを紹介します。
不動産投資・アパート経営の勉強をする
アパート経営の下準備は、まず不動産投資やアパート経営の基礎知識を身に着けることです。アパート経営の具体的なプランはコンサルタントや不動産投資コンサル会社に作ってもらいますが、知識なしの状態で依頼するのはリスクが高すぎます。内容を正確に理解できませんし、提案されたプランの良し悪しや目標との整合性なども判断できないためです。
具体的には、宅地建物取引業法・賃貸住宅管理業法などの法令や金融・建築の基礎知識、不動産投資にともなうリスクの種類などアパート経営に関する総合的知識が求められます。書籍での勉強が望ましいですが、効率的・専門的に学びたい場合はセミナーなども活用しましょう。
アパート経営に関する知識はあなたの資産を守るために役立ってくれます。資料の読み解き方一つで結果が大きく変わることもあるので、基礎知識は必ず身につけてから始めましょう。
競争力のある立地を選択する
収益物件は何より立地が大事です。もともと土地を所有している方が土地活用をする場合以外は、利便性が高く、将来性のある立地に建てられた物件を選択しましょう。立地選びで注目すべき点には、以下のような項目があります。
- 住宅需要の高さ
- 主要都市からの距離
- 交通状況
- 治安状況
- 周辺人口
- 周辺施設・周辺環境
- 都市計画・用途地域
- 地価の値動き
- 土地周辺の将来計画 など
立地が良い場所を見つけても、競合物件が多いと思い通りの結果が得られない可能性があります。需要と供給のバランスを見て、供給過多になっていないエリアを選択するようにしましょう。
リスクマネジメントを意識する
アパート経営には空室リスクや家賃滞納リスク、災害で資産を失うリスクなど、アパート経営特有のリスクがあります。どんな投資にリスクはつきものであり、不動産投資にもリスクは存在しますが、過剰に危険視する必要はありません。
アパート経営にともなうリスクのほとんどは事前に予測することができ、対策をとることができます。例えば空室リスクは競争力のある立地・間取りを選べば対処できますし、家賃滞納リスクには入居審査を適正に行うことでリスクヘッジが可能です。また、災害で資産を失うリスクは火災保険・地震保険への加入でリスク移転ができますし、ハザードマップを事前に見ておけば水害・津波を避けられます。
リスクマネジメントは、必要な対策を過不足なく講じることが大切です。
信頼できる管理会社を選ぶ
いかに物件の条件が良くても、適切な管理がなされなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。多くの実績とノウハウを持ち合わせており、専門的知見から賃貸経営を親身にサポートしてくれる管理会社を選びましょう。
この「親身にサポートしてくれる」という点は思った以上に重要です。積極的な姿勢が物件の評判の維持につながるからです。
適切な管理は入居者満足度を向上させ、物件の価値向上につながるでしょう。一方、問題のある管理が長期間放置されると、入居者は徐々に減り、アパート経営は悪化する可能性が出てきます。ゴミ捨て場の管理がきちんとされていないなどで周辺住民とのトラブルに発展したら、問題のあるアパートとして悪評が立ち、さらに物件の資産価値低下に拍車がかかりかねません。
まとめ
アパート経営はキャッシュフローがプラスになっただけでは成功とはいえません。健全なフローと保有資産の積み上げを両立して初めて、ひとまずの成功といえます。
また、アパート経営を安定させるためには信頼できるパートナーが不可欠です。管理会社の質によってリスク管理の度合いは変わってきます。
私たち大和財託は、お客様の人生に寄り添いながら資産を創っていくことを大切にしています。アパート経営においても一時の状況で判断せず、物件がお客様の人生を潤し続けることを前提にプランを作成します。
大和財託の賃貸管理では、管理戸数約6,500戸、平均入居率99.66 %、家賃回収率99.85%(令和6年6月末時点)と安心してお任せいただける水準を実現しています。個別無料相談も行っていますので、アパート経営をお考えの方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
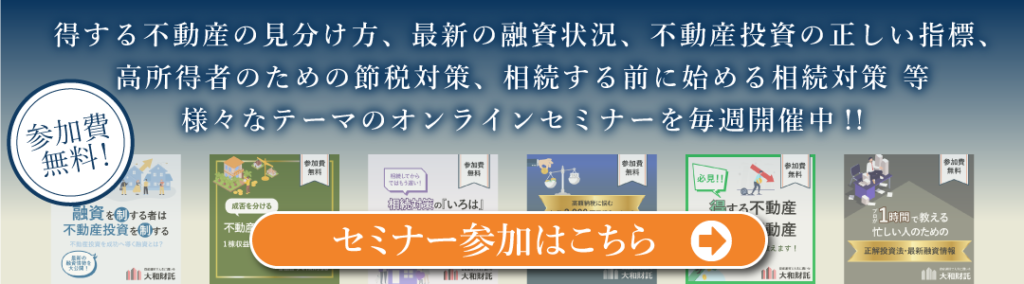
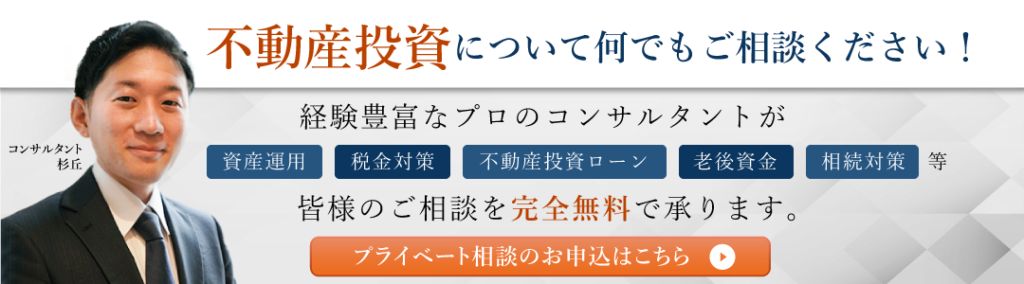
監修者

藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO
昭和55年生まれ 岩手県出身
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発業務に携わり、その後関東圏の不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
平成25年に大和財託株式会社を設立。不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を東京・大阪をはじめとする主要都市圏で展開する。
資産価値を創る様々なサービスを駆使し、“圧倒的顧客ファースト”を掲げ、お客様の人生に伴走しながら今までにない価値を開発・建築している。
自社で運営しているYouTubeチャンネル『藤原正明の「最強の不動産投資チャンネル」<大和財託株式会社>』やXといった様々なプラットフォームで資産運用についての知識や考え方を発信している。
書籍「収益性と節税を最大化させる不動産投資の成功法則」や「収益性と相続税対策を両立する土地活用の成功法則」を発売中。