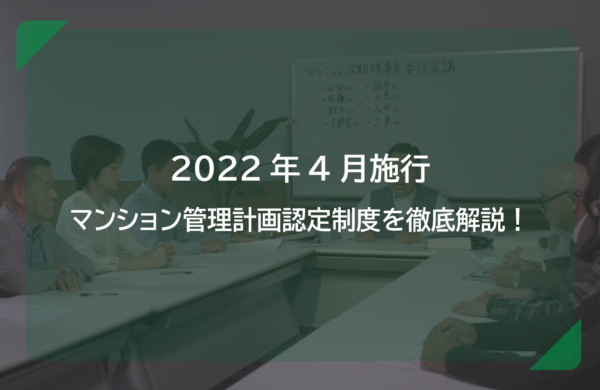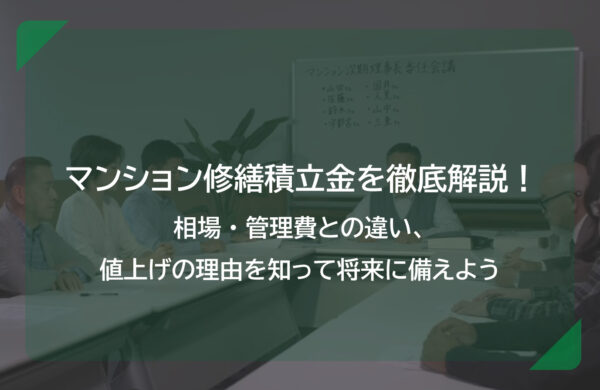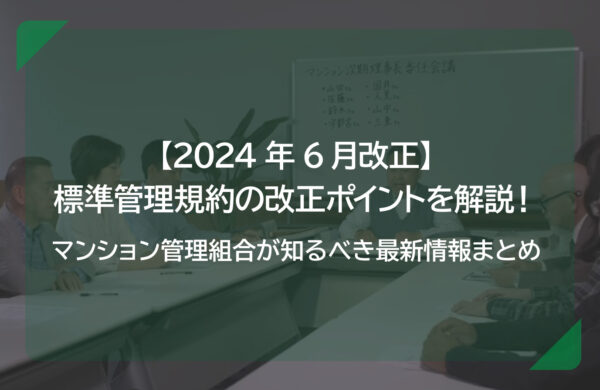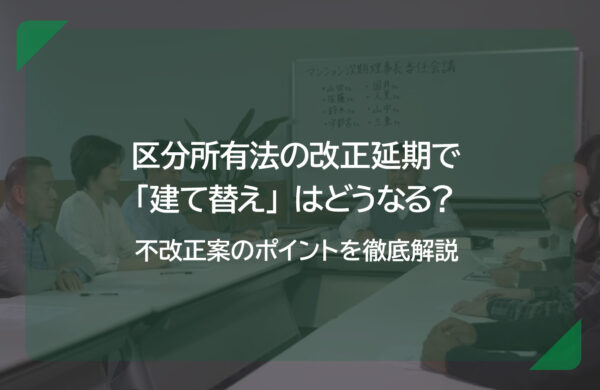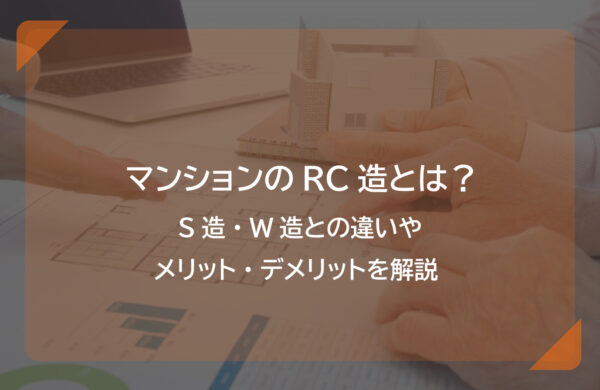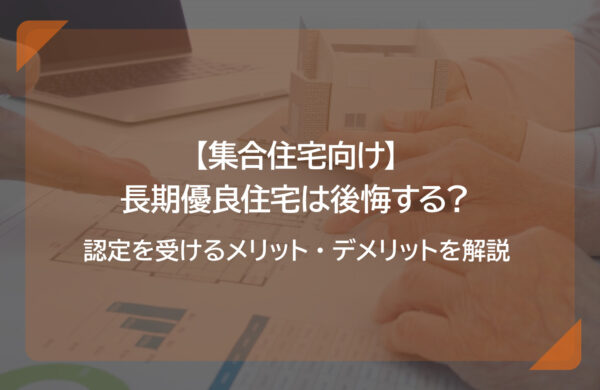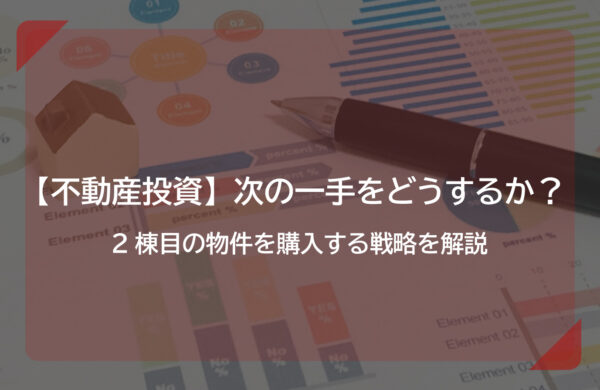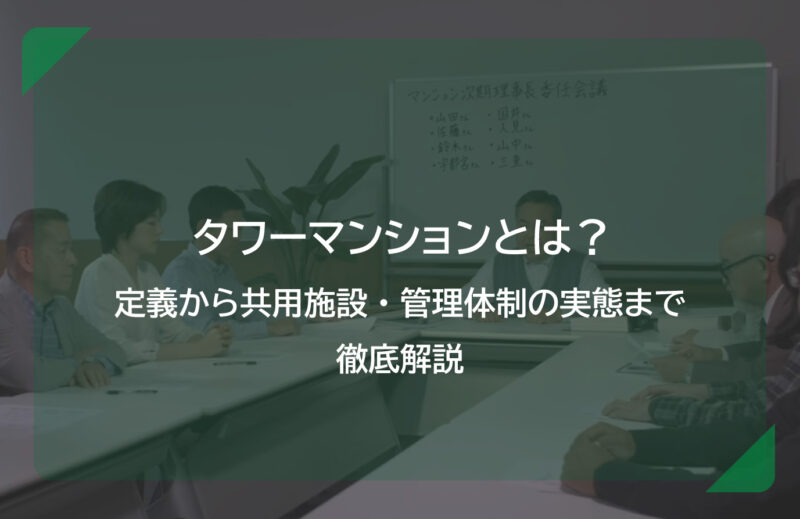
「タワーマンション(タワマン)」とは、一般的に20階以上の高層マンションを指す用語ですが、法律上の明確な定義はありません。そのため、物件ごとに設備や管理体制が大きく異なります。ジムやラウンジなど豪華な共用施設を備えた物件もあれば、最低限の設備のみのタワ-マンションも存在します。
本記事では、タワーマンションの定義や共用施設の特徴、管理体制の種類などを解説し、物件選びのポイントを分かりやすく紹介します。
目次
タワーマンションの定義とは?
タワーマンションと、都市部でよく見かける中高層マンションには、どのような違いがあるのでしょうか。ここでは、タワーマンションの定義や特徴を詳しく解説します。
タワーマンションの一般的な定義
タワーマンション(タワマン)には、明確な法的定義はありません。しかし、不動産業界では一般的に20階以上の高層マンションを指します。
また、建築基準法上、高さ60m以上の建築物は「超高層建築物」と定義されています。高さ60mの建物はおおよそ20階以上に相当するため、住居用の超高層建築物が「タワーマンション」と呼ばれることが多いのです。
ただし、これは厳密な基準ではなく、20階未満のマンションが「タワーマンション」として販売されるケースもあります。また、タワ-マンションには共用施設が充実しているイメージがありますが、物件によって設備や管理体制は大きく異なります。そのため、すべてのタワ-マンションが豪華とは限りません。
一方で、中高層マンションとは、一般的に4〜19階程度の階数を持つ集合住宅を指します。都市部では最も多く見られる住宅タイプで、4〜9階程度の「中層」、10〜19階程度の「高層(※タワマン未満)」の建物がこれに該当します。タワーマンションに比べるとスケールや共用施設はやや控えめな傾向にありますが、物件によっては設備が充実しているものも多く、バランスの取れた居住環境が魅力です。
タワーマンションと中高層マンションの違い
タワーマンションと中高層マンションは、階数や建築構造、共用施設、管理体制などに違いがあります。以下の表で、それぞれの特徴をまとめてみました。
| タワーマンション | 中高層なマンション | |
| 階数 | 20階以上 | 4〜19階程度 |
| 建築構造 | 免震・制震構造が採用されることが多い | 耐震構造が主流 |
| 共用施設 | 充実していることが多い(最低限の施設しかない物件もある) | タワーマンションに比べると少なめだが、大規模マンションでは充実している場合も多い |
| 管理体制 | 24時間有人管理の物件が多い | 物件によって異なる(24時間管理の中高層マンションもある) |
| 価格帯 | 高額になりがち | 物件によって幅広い |
ただし、共用施設が最低限のタワーマンションもあり、管理体制は一律ではありません。特に、価格帯の低いタワーマンションにはゲストルームやスカイラウンジなどの施設がないケースも珍しくありません。
そのため、単に「タワマンだから設備が充実している」と考えず、一つひとつの物件をしっかり確認することが重要です。
タワーマンションの共用施設とは?
タワーマンションの魅力の一つは、中高層マンションにはない多彩な共用施設です。しかし、物件によって設備の内容や管理体制は大きく変わります。各物件の設備や維持管理の状況をしっかり確認し、自分に合ったタワーマンションを選びましょう。
一般的なタワーマンションに備わっている主な共用施設
タワーマンションの共用施設は物件ごとに異なり、充実した設備を備えた物件もあれば、最低限の施設のみの物件もあります。設備が充実しているほど管理費が高額になる傾向があるため、各設備の有無だけでなく、維持管理の質も確認しましょう。
以下の表で、タワーマンションに多く見られる代表的な共用施設を紹介します。
| 共用施設 | 内容 |
| ゲストルーム | 来客者が宿泊できる部屋。予約制が一般的で、ホテルのような設備を備える物件もある |
| ラウンジ・スカイラウンジ | 眺望を楽しみながら住民がくつろげるスペース。高層階に設置されることが多い |
| フィットネスジム | 居住者専用のトレーニング施設。24時間利用可能な物件もあり、健康志向の住民に人気 |
| パーティールーム | 住民同士のイベントや家族・友人との集まりに利用可能。キッチン付きの物件もある |
| ワークスペース | テレワークの普及により増えている設備。Wi-Fi完備で会議室付きの物件もある |
| コンシェルジュサービス | 宅配便の受け取り、タクシー・クリーニングの手配などを行う。高級タワ-マンションで採用されることが多い |
各物件の共用施設をチェックする際は、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。
- 管理費を確認する
→共用施設が充実しているほど管理費が高くなる傾向がある
- 利用ルールや予約の有無を事前に確認する
→施設によっては予約制・利用時間の制限などがある
- 設備の維持管理が行き届いているかをチェックする
→設備があっても適切に管理・清掃されていなければ快適に利用できない
すべてのタワーマンションが豪華な施設を持つわけではない
前述のとおり、すべてのタワーマンションに豪華な共用施設が備わっているわけではありません。共用施設を最低限に抑えたタワーマンションの特徴として、以下のような例が挙げられます。
- ゲストルームやスカイラウンジが設置されていない
- 管理員が平日昼間のみ在籍し、夜間・休日は無人管理
- エントランスや駐車場程度の共用施設しかない
共用施設の充実度は物件ごとに異なるため、事前の確認が不可欠です。
また、共用施設の維持費は管理費から捻出されるため、利用頻度が低い共用施設が多いと、管理費が割高に感じる可能性があります。そのため、本当に必要な共用施設を選別し、自分のライフスタイルに合ったタワーマンションを選ぶことが重要です。
タワーマンションの管理体制と生活環境
タワーマンションを選ぶ際は、共用施設の充実度だけでなく、管理体制や生活のしやすさ(セキュリティ対策やゴミ出しのルールなど)も重要なポイント です。また、建物の耐震性や周辺環境(立地条件、交通アクセス、周辺施設の充実度など)も事前に確認しておきましょう。タワーマンションを選ぶ際は、共用施設の充実度だけでなく、管理体制や生活のしやすさ(セキュリティ対策やゴミ出しのルールなど)も重要なポイント です。また、建物の耐震性や周辺環境(立地条件、交通アクセス、周辺施設の充実度など)も事前に確認しておきましょう。
セキュリティ対策
タワーマンションでは、防犯対策が充実していることが一般的です。特にエントランスや共用部は、2重・3重はもちろん、最近では5重のセキュリティを採用するタワーマンションもあります。
5重のセキュリティ対策では、敷地内に入ると防犯カメラで監視が開始されます。次に、風除室(エントランス手前)でカメラ付き集合インターホンを通じて訪問先の居住者が確認し、認証後にオートロックを解除。さらに、エントランスホールで再度同様の確認が行われ、建物の内部に続く扉が開きます。その後、エレベーターは訪問先の階にのみ停止するよう自動制御され、不審者の移動を制限し、最後に住戸玄関のカメラ付きインターホンで最終確認が行われ、安全が確保された上で入室が許可される仕組みです。
また、24時間体制で管理員や警備員が常駐している物件では、常に有人での見守りが行われ、不審者の侵入を防いでいます。近年では、エレベーターにカードキー認証を導入し、住戸フロア以外の階に行けない物件も増えています。
ゴミ出しルール
タワーマンションのゴミ出しルールは物件によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
一般的に、各階にゴミステーションが設置されている物件が多く、24時間いつでもゴミを捨てられるケースもあります。特に高層階の住民にとっては、1階まで降りる手間が省けるため、利便性が向上します。
暮らしのルール
タワーマンションには、中高層マンションとは異なる生活ルールが設けられていることがあります。
たとえば、高層階の強風による落下の危険性や景観維持の観点から、洗濯物の外干しを禁止している物件もあります。
また、近年ではペット可の物件が増えていますが、動物の種類や体重に制限があるケースも珍しくありません。さらに、共用部分の移動では、キャリーバッグの使用が義務付けされていたり、ペット専用のエレベーターを使用するルールがある物件もあります。
立地環境
タワーマンションの多くは、駅近の好立地にあり、通勤・通学が便利です。特に都市部では、駅からの距離が生活の利便性や資産価値に大きく影響します。また、ショッピングセンターやスーパーマーケット、医療機関、レストランなど、生活に必要な施設が周辺に整っている物件が多いことも特徴です。
近年では、郊外や地方都市、再開発地域にもタワ-マンションが建設されるケースが増えています。たとえば千葉県「柏の葉キャンパス(柏の葉スマートシティ)」では、タワーマンションの建設と同時に、商業施設や研究機関、公園などが整備されています。また海に近いエリアでは、リゾート感覚で暮らせるタワーマンションもあるため、ライフスタイルに応じた物件選びが可能です。
他にも、駅直結型のタワーマンションや、商業施設と一体になった複合型タワーマンション、医療機関や行政施設を併設した機能性重視のタワーマンションなども増えており、利便性の高い住環境が整っています。
地震への対策
タワーマンションでは、上層階になるほど建物の揺れは大きくなるため、地震対策が欠かせません。
| 構造 | 特徴 |
| 免震構造 | 建物と地盤の間に免震装置を設置し、地震の揺れを大幅に軽減。家具の転倒リスクも抑えられる |
| 制震構造 | 建物内部に制震装置を設置し、地震の揺れを吸収・軽減。建物の変形を最小限に抑える |
| 耐震構造 | 柱や梁を強化し、地震の揺れに耐える。中高層マンションや戸建て住宅に多い構造 |
ほとんどの戸建て住宅や中高層マンションは耐震構造ですが、揺れが大きくなるタワーマンションでは、免震構造や制震構造が採用されるケースが多くなっています。
また、最近のタワーマンションでは、免震構造と制震構造を組み合わせた物件も増えており、地震対策のレベルは物件ごとに異なります。
地震対策としては、建物の構造だけでなく、非常用発電機・備蓄倉庫・防災センターの有無も確認しておくと安心です。また、防災委員会を設置し、住民の防災意識を高める取り組みを行っている物件もあります。
タワーマンション選びで後悔しないために優先順位を整理しよう
タワーマンションとは、一般的には20階以上の高層マンションを指す言葉です。しかし、設備や管理体制、共用施設の充実度は物件ごとに異なります。そのため、自分が重視するポイントを整理し、優先順位をつけることが重要です。また、セキュリティ対策やゴミ出しルール、生活ルール、地震対策なども事前に確認しておくことで、より安心して暮らせるタワーマンション選びができます。
さらに、「タワマン節税」など、タワーマンションに関する税制面の情報を知りたい方は、ぜひ以下のコラムもチェックしてみてください。
監修者

藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO
昭和55年生まれ 岩手県出身
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発業務に携わり、その後関東圏の不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
平成25年に大和財託株式会社を設立。不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を東京・大阪をはじめとする主要都市圏で展開する。
資産価値を創る様々なサービスを駆使し、“圧倒的顧客ファースト”を掲げ、お客様の人生に伴走しながら今までにない価値を開発・建築している。
自社で運営しているYouTubeチャンネル『藤原正明の「最強の不動産投資チャンネル」<大和財託株式会社>』やXといった様々なプラットフォームで資産運用についての知識や考え方を発信している。
書籍「収益性と節税を最大化させる不動産投資の成功法則」や「収益性と相続税対策を両立する土地活用の成功法則」を発売中。