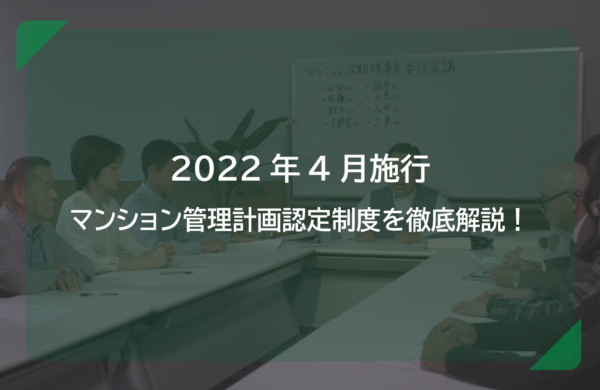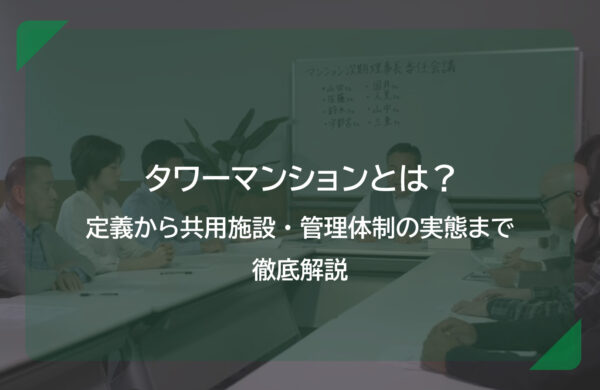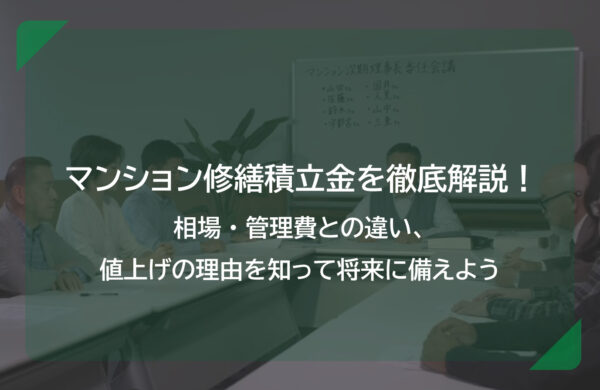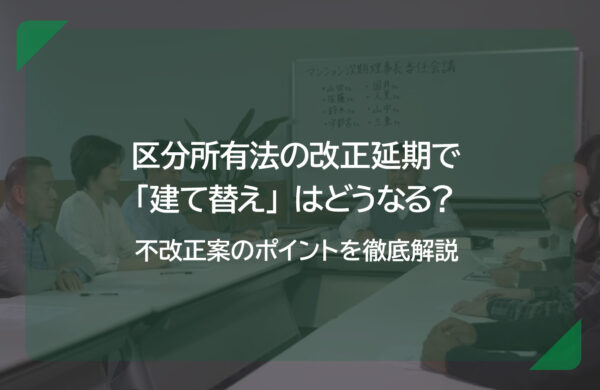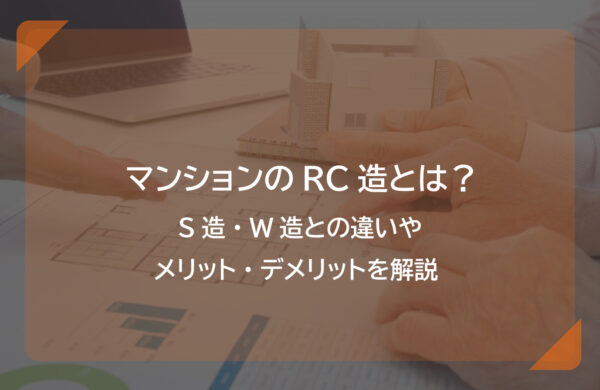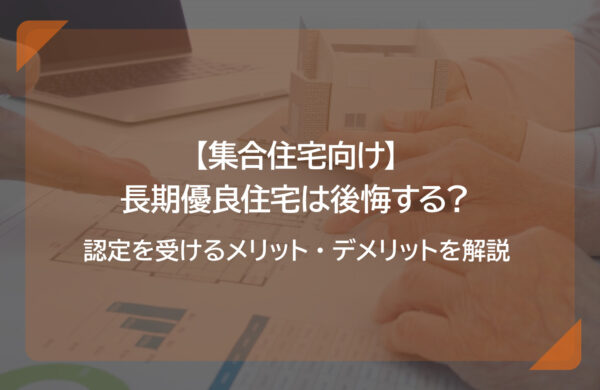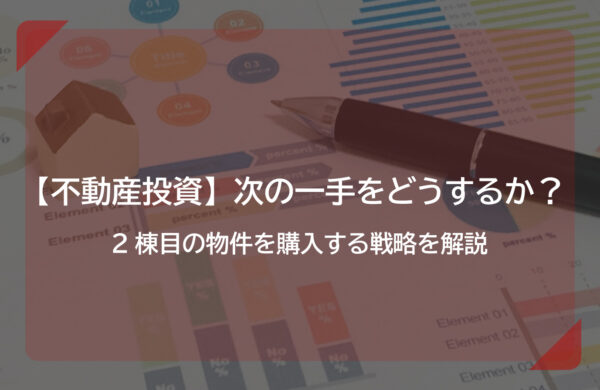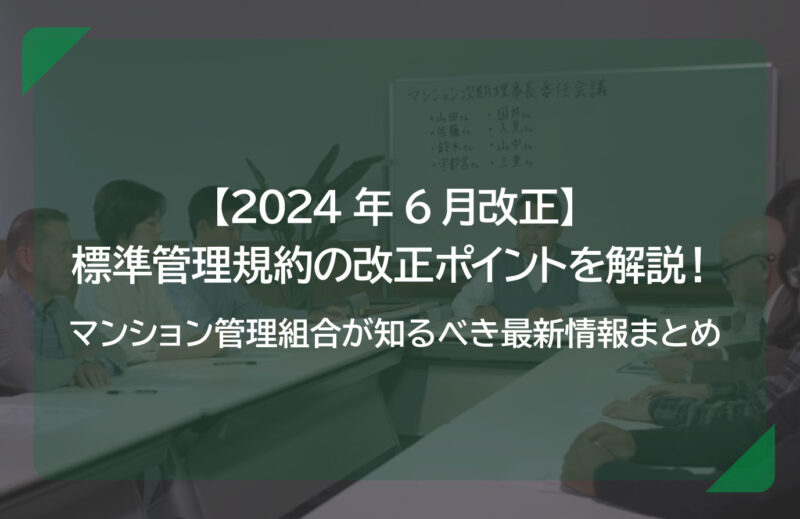
2024年6月、「標準管理規約」が改正されました。
標準管理規約とは、マンションの共用部分の管理方法、修繕積立金の運用、理事会の運営などを定める「管理規約」の標準的なモデルです。区分所有法に基づいて国土交通省が定めており、各マンションの管理組合が管理規約を定める際のひな形として利用されています。
本記事では、2024年6月の標準管理規約の改正が注目される理由や社会的な背景、改正のポイントを解説します。
目次
マンションの標準管理規約が2024年6月に改正された背景とは?
2024年6月に行われた標準管理規約の改正は、マンションの高経年化と居住者の高齢化、管理情報の見える化の推進、社会情勢やライフスタイルの変化への対応といった現代の課題に対応するために実施されました。
マンションの高経年化と居住者の高齢化は「2つの老い」とも呼ばれています。
高経年マンションでは、マンションに居住していない外部区分所有者や、現住所が不明な区分所有者が多く見られる傾向があります。連絡がつかない区分所有者が多いと理事の選任や修繕工事といった重要な決議が滞り、マンションの維持・管理が困難になってしまいます。
さらに近年では、家族構成やライフスタイルも多様になりました。時代の変化に伴う新たなニーズの増加も、今回の標準管理規約改正の背景にあります。
マンションの管理規約とは何か詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。
【マンションの管理規約とは?使用細則との違いや確認方法解説】
マンションの標準管理規約の主な改正ポイント
ここでは、2024年6月の標準管理規約改正におけるポイントを以下5点に分けて解説します。
組合員名簿等の作成・更新の仕組みを明確化
組合員と居住者の情報管理に関するルールが明確化されました。区分所有者がそのマンションに住んでいない場合でも連絡が取りやすくなり、マンション管理をより円滑に行えるようになることが期待されています。
具体的な改正ポイントは以下のとおりです。
- 住所変更の届け出が必要:マンションを所有する組合員が住所を変更した場合、書面で管理組合に届け出る
- 賃貸時の情報提供:部屋を貸し出す場合、借り主の氏名や連絡先を管理組合に通知する
- 居住者名簿の作成:賃借人を含む居住者全員の氏名や連絡先を記録した「居住者名簿」を作成する。また、災害時の避難で配慮が必要な人(高齢者、障害者、乳幼児など)を把握しておくことが望ましい
- 組合員名簿の定期更新:内容に変更がなくても、少なくとも年に1回は組合員名簿の内容を確認する
- 所在不明の区分所有者への対応:所在がわからない区分所有者のためにマンション管理に支障が生じている場合、または支障が生じる恐れがある場合、理事会決議で調査することができる。また、その調査にかかった費用は調査された区分所有者に請求できる
電気自動車(EV)充電設備の設置を推進
電気自動車(EV)の普及を受け、マンションでのEV充電設備の導入が進みやすくなるよう、管理規約へ記載する場合の方針が示されました。これにより、居住者の利便性向上や環境に配慮した暮らしの実現が期待されています。
具体的なポイントは以下のとおりです。
- 充電設備利用ルールの設定:充電設備の利用方法や使用料を駐車場の利用規則などに明記することが望ましい
- 費用負担の詳細を決める:充電設備の設置費用や維持費を誰が負担するのか、またその割合を事前に総会で決議することが望ましい
- 設置工事の決定が簡単に:建物の構造部分や敷地に一定程度の変更が生じない限り、総会の普通決議(組合員の過半数の賛成で可決される決議)で充電設備の設置工事が可能と考えられる
- マンション購入時の情報提供:当該マンションを購入しようとする人に対する管理情報提供項目例に、「EV充電設備の有無」を追加する
宅配ボックスの管理・利用ルールを明確化
宅配ボックスの需要が高まっているにもかかわらず、宅配ボックス設置工事の決議要件が具体的に示されていませんでした。そこで今回の改正では、宅配ボックスの設置に関する決議要件が以下のように明確化されました。
- 宅配ボックスの設置工事に関して、壁や床に軽く固定する程度で共用部分の加工の程度が小さい場合は、総会の普通決議(出席者の過半数の賛成)で設置工事の実施が可能と考えられる
また、置き配に関する使用細則を定める際のポイントも記載されました。具体的には以下のとおりです。
- 置き配可能な時間や場所を具体的に設定すること:例えば、○時~○時の間のみ置き配サービスを利用できる、専有部分の玄関前のみ荷物を置くことが可能、通行や避難の妨げとなる場所や、設備が破損する可能性がある場所に置くことは禁止など
- 宅配物を保管できる期間を定めること:例えば、配達日の当日中までなら留め置くことが可能、24時間以上放置することを禁止するなど
- 置き配できない宅配物を具体的に定めること:例えば、衛生上問題のあるもの、強い臭いを発するもの、発火・引火・爆発の危険があるものは禁止など
- ルール違反に対する対応方法をあらかじめ定めておくこと:例えば、管理組合が違反する宅配物を確認した際、置き配サービスを依頼した人に対して荷物の引き取りや対応の修正を求めることができる、もしその指示に従わない場合、管理組合は宅配物を移動するといった措置を取ることができるなど
- 置き配の依頼や宅配物の管理に関する責任の所在を明確化すること:例えば、区分所有者が置き配サービスの依頼や宅配物の管理を自分の責任で行う、管理組合やマンション管理会社はこれに関して一切の責任を負わないなど
- 消防法に基づき、廊下や階段、避難口など、緊急時の避難を妨げる場所への宅配物の放置を禁止すること
修繕積立金の積立状況などを可視化
共用部分の修繕・維持管理のために組合員全員が積み立てる「修繕積立金」の管理に透明性を持たせるため、新たなコメントが盛り込まれました。
現在の積立金額や変更予定について総会で確認する仕組みが提示され、将来の修繕や必要な工事に向けた計画がより立てやすくなりました。
具体的なポイントは以下のとおりです。
- 積立状況の報告に関するコメントの追加:毎年の総会で、長期修繕計画上の積立予定金額と現在の積立状況の差を資料を用いて説明し、修繕資金の充足状況を組合員全員が把握することが有用
- 修繕積立金の変更予定に関するコメントの追加:毎月の積立額を変更する必要がある場合、変更の時期や変更後の予定金額を事前に説明することが有用
マンション購入予定者への情報提供:当該マンションを購入しようとする人に対する管理情報提供の項目例に、修繕積立金の変更予定時期と変更後の予定金額を追加
総会関連の資料の保管が義務化
総会で使用した議案書や関連資料を保管しなければならない旨と、組合員や利害関係者が総会の議案書や関連資料を見せてほしいと請求した場合には、閲覧できるようにしなければならない旨が追加されました。さらに、理事会資料についても総会資料に準じた保管義務が明記されました。
改正前の標準管理規約では総会議事録の保管義務に関する規定はあったものの、そのほかの資料の保管については明記されていませんでした。今回の改正で、議事録以外の総会資料や理事会資料の保管・閲覧に関するルールが明確化され、管理の透明性が強化されたといえます。
また、管理規約を変更した場合、原本とは別に変更内容を反映した冊子を作成することが望ましい旨もコメントに記載されました。
標準管理規約に準拠した規約への改正の流れ
改正後の標準管理規約には、所在不明区分所有者への対応や、現代の暮らしに必要なルールが追加されています。理事会などで内容を確認し、自分のマンションの管理規約を見直してみるとよいでしょう。
ここでは、管理規約改正の流れを以下の4ステップに分けて解説します。
【第1ステップ】 理事会で改正内容を確認・検討する
まずは理事会で標準管理規約の改正内容を確認し、管理規約改正の必要性を検討しましょう。必要に応じて、規約改正を専門的に検討する委員会を設置する場合もあります。委員会は理事や有志の組合員で構成され、外部の専門家を招くこともあります。ただし小規模マンションでは、委員会を設置せずに理事会で検討を進めるケースが一般的です。
メンバーが決まったら理事会または委員会で現行の規約を精査し、改正が必要な点を洗い出しましょう。
【第2ステップ】組合員への情報共有と説明会を開催する
改正案が完成したら、組合員全員に内容をしっかり伝えましょう。その際、改正案を配布して、誰でも簡単に確認できる方法を用意することが大切です。
特に大幅な変更を含む場合には規約の説明会や意見交換会を開催し、疑問を解消することが求められます。組合員から寄せられた意見を理事会で精査し、必要に応じて改正案の修正と最終調整を行いましょう。
【第3ステップ】総会での承認と改正作業を行う
改正案がまとまったら総会を開催し、承認を求めましょう。
区分所有法に基づき、管理規約の改正には総会での「特別決議」が必要です。特別決議は、組合員数および議決権数の各4分の3以上の賛成が必要です。
【第4ステップ】新ルールの施行と周知を徹底する
改正後の管理規約が総会で承認されたら、正式に施行されます。
全組合員に対して新しい規約を確実に周知するため、修正された規約を配布したり、改正個所の概要を掲示板で周知したりしましょう。必要に応じて、デジタル配布も活用すると効果的です。
管理規約を改正する時のポイント
管理規約を改正する時のポイント
組合員の理解と協力が大切
管理規約の改正には、組合員数および議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要となります。そのため、組合員全員の理解と協力を得られるよう努めましょう。
組合員の意見を集めて反映することで、スムーズに合意形成しやすくなります。アンケートや説明会など、質問や意見を吸い上げる場を設けるとよいでしょう。匿名で意見を募れば、より率直な声を集められます。
ただし、匿名アンケートでさまざまな意見が寄せられるとすべての意見を反映できなくなり、収拾がつかなくなる恐れもあります。規約改正が遅れるリスクもあるため、メリット・デメリットを踏まえて実施の要否を検討しましょう。
専門家の力を借りる
管理規約の改正に法律的な問題や技術的な問題が含まれる場合、専門家の助言を受けるとよいでしょう。
例えば、マンション管理士はマンション管理の専門家です。管理規約や使用細則に関する専門的な知識を持っており、改正の内容や手続きについてアドバイスしてもらえます。
こうした専門家を活用すれば、組合員から寄せられる疑問や法的リスクの解消をよりスムーズに進められるでしょう。
マンション管理を一段と向上させるチャンス!より良いマンション運営を目指そう
2024年6月の標準管理規約改正では、マンション管理の透明性や効率性を向上させ、トラブル防止や住環境の改善につながる内容が盛り込まれました。時代背景やニーズの変化に応じて新しいルールを取り入れれば、より安心感のあるマンション管理が実施できるでしょう。
管理規約改正を検討する際は、専門家を活用することで、合意形成や改正作業をスムーズに進められます。適切なタイミングで専門家やコンサルティングサービスを活用することが、効率的な管理規約改正の鍵となります。
監修者

藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO
昭和55年生まれ 岩手県出身
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発業務に携わり、その後関東圏の不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
平成25年に大和財託株式会社を設立。不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を東京・大阪をはじめとする主要都市圏で展開する。
資産価値を創る様々なサービスを駆使し、“圧倒的顧客ファースト”を掲げ、お客様の人生に伴走しながら今までにない価値を開発・建築している。
自社で運営しているYouTubeチャンネル『藤原正明の「最強の不動産投資チャンネル」<大和財託株式会社>』やXといった様々なプラットフォームで資産運用についての知識や考え方を発信している。
書籍「収益性と節税を最大化させる不動産投資の成功法則」や「収益性と相続税対策を両立する土地活用の成功法則」を発売中。