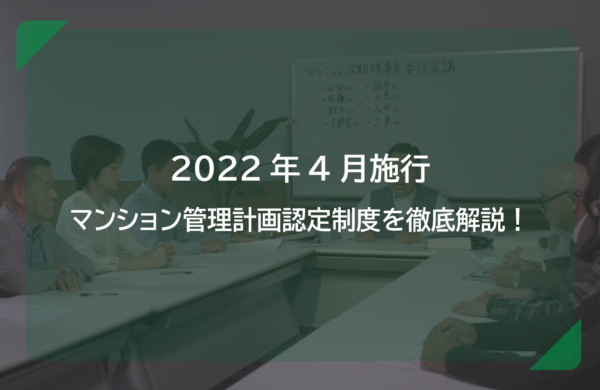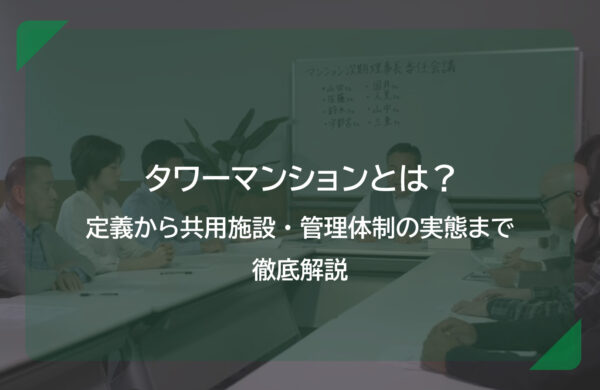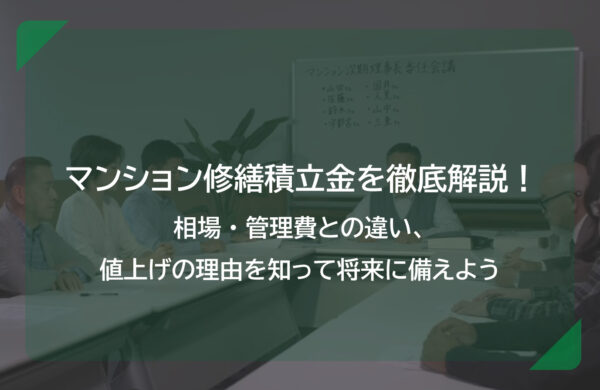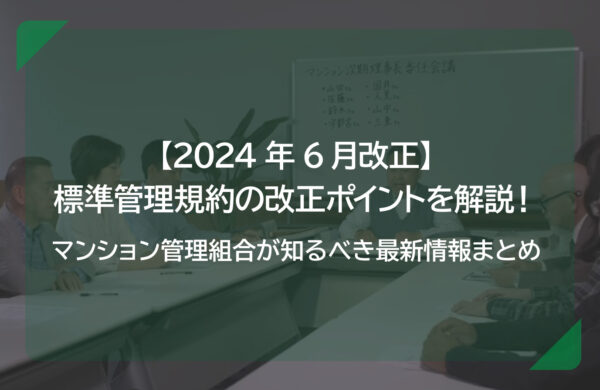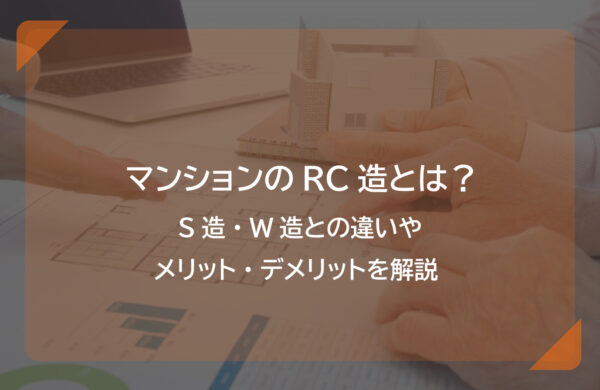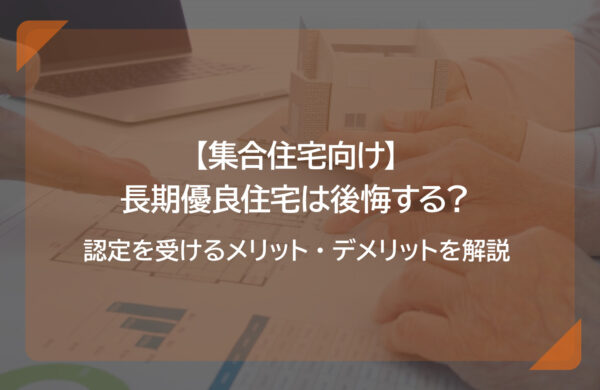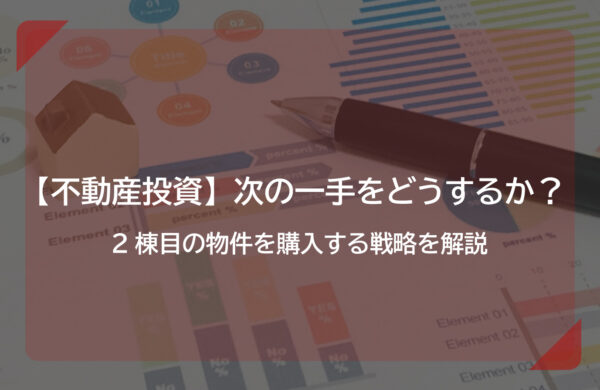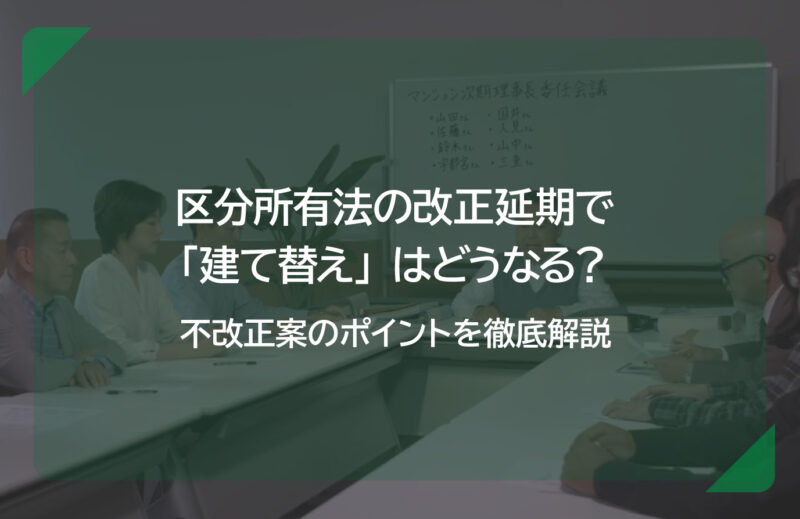
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)は、分譲マンションなどの集合住宅のように、一棟の建物が二つ以上の部屋に区切られ、その部屋がそれぞれの所有権の対象となる「区分所有建物」に関する権利や管理について定める法律です。分譲マンションに限らず、オフィスビルや商業施設でも、各部屋が構造や用途の面で独立していれば区分所有が成立します。区分所有法は近年のマンション問題を受け、2024年に改正される予定でしたが、国会審議が進まず延期されました。
今回の改正案の中で特に注目を集めたのが、一定の条件下での「建て替え決議要件」の緩和です。改正の延期を受けて、マンションの建て替えや将来の管理について不安を覚えるマンション所有者、管理組合も多いでしょう。
本記事では、区分所有法改正案で特に注目を集める建て替え決議要件を中心に、改正の背景や改正内容のポイントを詳しく解説します。
目次
区分所有法が改正される背景とは?
2024年度の国会で審議予定だった改正案は、会期中に十分な審議時間が確保できず延期されました。しかし改正案が破棄されたわけではなく、改正の背景にあるマンションの老朽化や居住者・組合員の高齢化、耐震性の確保といった問題に対応するため、今後改めて議論される予定です。
ここでは、区分所有法改正の背景や建て替えの必要性を改めて解説します。
老朽化マンション問題の深刻化
国土交通省のデータによれば、2023年末時点で日本の分譲マンション総数は約704.3万戸です。そのうち築40年以上のマンションは約125.7万戸に上り、さらに10年後には約2倍の260.8万戸、20年後には約3.5倍の445.0万戸に増加すると予測されています。老朽化したマンションの多くは耐震性に問題があり、地震大国・日本において深刻なリスクとなっています。
しかし現行の区分所有法では、マンションの建て替えを行うには区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要です(区分所有法62条1項)。この決議要件は非常にハードルが高いため老朽化したマンションの建て替えを妨げる要因となっており、より柔軟に建て替えを行うための改正が求められています。
参考:国土交通省「分譲マンションストック数の推移(2023年末現在)」
居住者の高齢化による管理組合の機能低下
国土交通省「令和5年度マンション総合調査」によると、世帯主が70歳以上のマンションの割合は25.9%であり、平成30年度に行われた前回調査から3.7ポイント増加しています。特に高経年のマンションでは高齢化が顕著です。
高齢の所有者が多いマンションでは、管理組合役員のなり手不足や運営能力の低下といった問題が起こりがちです。修繕積立金が不足して工事資金が確保できないケースや所有者がそのマンションに居住していないケースも多くなり、建て替えや修繕工事などの重要な決定が滞ってしまうマンションも珍しくありません。
管理組合がスムーズに工事計画を主導できるよう、迅速に意思決定できる法整備が求められています。
参考:国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果からみたマンションの居住と管理の現状」
安全性の確保と耐震基準の見直し
日本は地震が頻発する国であり、高経年マンションの耐震性の確保が必要です。特に、1981年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準(旧耐震基準)で建設されたマンションは耐震性が十分でない可能性があるため、耐震診断や耐震改修の実施が求められています。
国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」によると、旧耐震基準で建築されたマンションのうち、耐震診断を実施した割合は約31.6%に留まっています。また、十分な耐震性がないと判断されたマンションのうち、「耐震改修を実施する予定がない」と回答したものの割合は25.0%にも上りました。
居住者や近隣住民の安全確保のため、耐震診断や改修工事を進める明確なガイドラインや法律の整備が求められています。
現行の区分所有法で生じる「建て替え問題」
現行の区分所有法ではマンションを取り巻く課題に対応しきれず、さまざまな問題が生じています。ここでは、特に建て替えに関する問題を解説します。
合意形成が難しい
同じマンションの所有者でも経済状況や生活環境はさまざまであり、意見の統一は困難です。特に建て替えには莫大な費用がかかるため、工事資金を捻出するのが苦しいといった理由で反対する所有者も多くいます。
また、所有者の年齢や居住形態が多様化すると意見が対立しやすくなります。これからも長く住み続けたい若年層は建て替えの意欲が高くても、高齢者やマンションに居住していない賃貸オーナーは建て替えのメリットを感じにくい場合があるためです。高齢者の中には、建て替え工事中の仮住まいへの転居を負担に感じる人もいるでしょう。
このように所有者同士で利害が一致しない場合、建て替えに必要な賛成数を得られず、マンションが老朽化しているにもかかわらず建て替えが進まない事態に陥りやすくなります。
マンションが老朽化すると建物の安全性が低下し、適切な修繕や建て替えが行われなければ資産価値も下がります。その影響で、所有者が次々と手放そうとしても買い手が見つからず、修繕積立金の不足がさらに深刻化。結果として修繕や維持管理が難しくなり、老朽化が一層進むという悪循環に陥る可能性が高まります。
建て替えに反対する区分所有者がいることで計画が停滞する
大多数の所有者が建て替えを望んでいても、建て替えに反対、または決議に参加しない少数の所有者がいる場合、計画全体が大幅に遅れる可能性があります。
建て替えを主導する管理組合は、建て替えに賛成しない所有者の権利を買い取る必要がありますが、売渡請求の手続きや適正価格の算定が複雑なため、建て替えが遅れる要因になります。
また、賃貸目的で複数の部屋を所有しているオーナーや地権者など、1人で多くの議決権を持つケースもあります。建て替えの決議では、所有者の人数だけでなく議決権の5分の4以上の賛成が必要なため、こうしたオーナーの意向が大きく影響します。さらに、高経年マンションでは、海外在住で連絡が取りにくい所有者や、管理に関心のない所有者も少なくありません。その結果、総会での賛成票が不足し、建て替えが進みにくくなる要因となることがあります。
特に賃貸オーナーの中には、建て替えによる長期的なメリットよりも短期的な収益を優先する人もいます。その結果、実際に居住する所有者の安全性や快適さが後回しにされるケースも少なくありません。
区分所有法改正における「建て替え」ポイント
老朽化したマンションの再生をより円滑に進めるため、今回の区分所有法改正案では建て替えに関する具体的な改善策がいくつか提案されました。それぞれのポイントを詳しく解説します。
建て替え決議要件の緩和
現行法では、建て替えの決議には「区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成」が必要です。
今回の改正案でも基本的な多数決割合は変わらないものの、耐震性が不足している、建物が老朽化している、居住者の安全性が脅かされるリスクがあるといった客観的事由がある場合は、建て替えの決議要件を「所有者および議決権の各4分の3以上の賛成」に緩和する提案がされました。
建て替え決議がされた際の賃貸借契約の終了
改正案では、建て替え決議が成立したときに所有者から住戸を借りて居住している賃借人がいる場合、その賃貸借契約が終了することが明記されました。
建て替え決議後から賃貸借契約終了までは一定の期間が設けられ、引っ越し費用や借主が受ける損害を補償する仕組みも提案されています。
所在不明者の同意要件の緩和
現行法では所在不明者(現在どこに住んでいるのかわからない所有者)も、決議に必要な所有者数および議決権の母数に含まれます。これが原因で決議要件を満たせず、建て替えや管理組合の運営に支障をきたすケースが問題となっていました。
改正案では、建て替えを進める管理組合が裁判所に申し立てることで、所在不明者を所有者数および議決権数の母数から除外できる案が盛り込まれました。この案が実現されれば、建て替えをはじめ、重要な意思決定の障壁を取り除きやすくなります。
区分所有法改正案のメリット
区分所有法の改正案では、これまで抱えていた課題を改善するべくさまざまな提案がされました。具体的なメリットは以下のとおりです。
①建て替えが進みやすくなる
一定の客観的要件を満たした場合に決議要件が引き下げられる案が実現すれば、老朽化が進んだマンションの建て替えを進めやすくなります。
②決議後に賃貸借契約を終了できる
建て替えに伴う賃貸借契約の終了が明記され、賃貸人に対する補償の内容も盛り込まれることで、決議後に賃貸借契約を終了できるようになり、建て替えがスムーズに進むことが期待されます。
区分所有法改正案の実現で老朽化マンションの再生が加速!
区分所有法の改正案が実現すればマンション建て替えのハードルが大幅に低下し、老朽化したマンションの再生が進みやすくなります。手続きを踏んだうえで所在不明者を決議要件の母数から除外することも可能になり、合意形成がスムーズに進みやすくなるでしょう。
ただし、建て替えを進めるには、法的手続きや資金計画などの複雑な準備が必要です。弁護士や不動産コンサルタントといった専門家のサポートが成功の鍵を握ります。
建て替えについて課題を抱えている方、また「管理組合の運営を第三者に任せる第三者管理方式に移行したい」「管理会社を変更したい」「大規模修繕工事やリノベーション工事を進めたい」といったお悩みをお持ちの方は、大和財託にご相談ください。マンションの資産価値を第一に考えたサポートを提供します。
監修者

藤原 正明/大和財託株式会社 代表取締役CEO
昭和55年生まれ 岩手県出身
三井不動産レジデンシャル株式会社で分譲マンション開発業務に携わり、その後関東圏の不動産会社で収益不動産の売買・管理の実務経験を積む。
平成25年に大和財託株式会社を設立。不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を東京・大阪をはじめとする主要都市圏で展開する。
資産価値を創る様々なサービスを駆使し、“圧倒的顧客ファースト”を掲げ、お客様の人生に伴走しながら今までにない価値を開発・建築している。
自社で運営しているYouTubeチャンネル『藤原正明の「最強の不動産投資チャンネル」<大和財託株式会社>』やXといった様々なプラットフォームで資産運用についての知識や考え方を発信している。
書籍「収益性と節税を最大化させる不動産投資の成功法則」や「収益性と相続税対策を両立する土地活用の成功法則」を発売中。