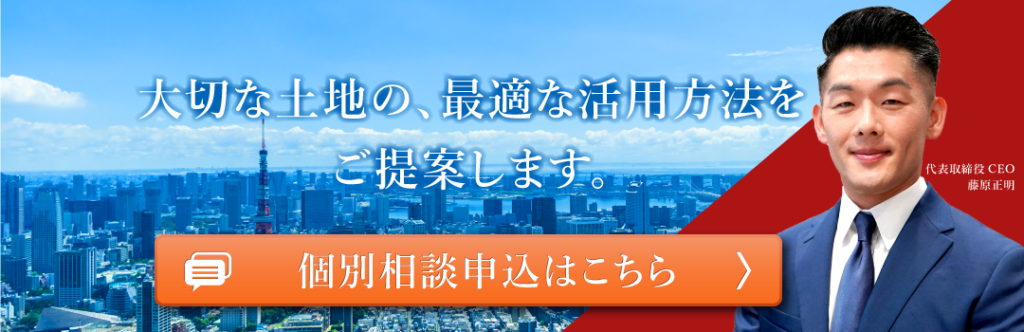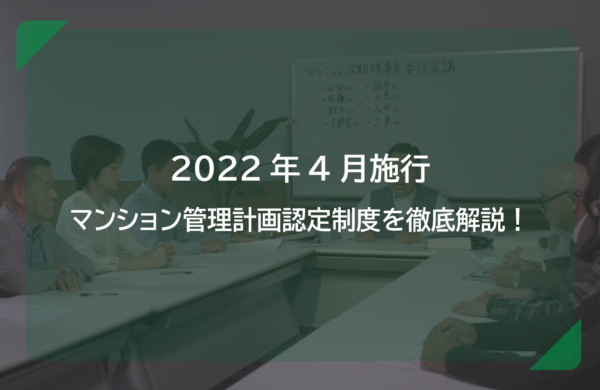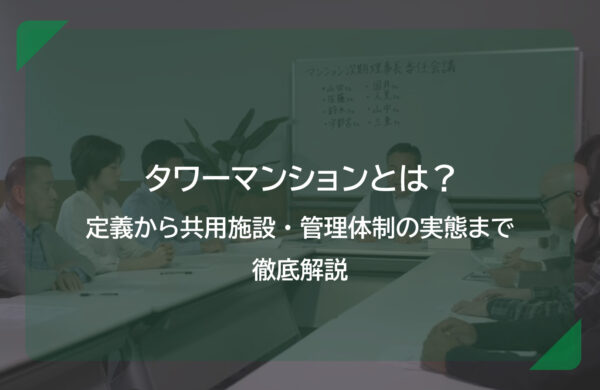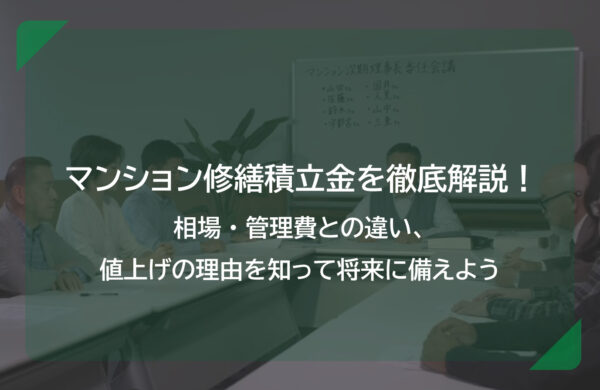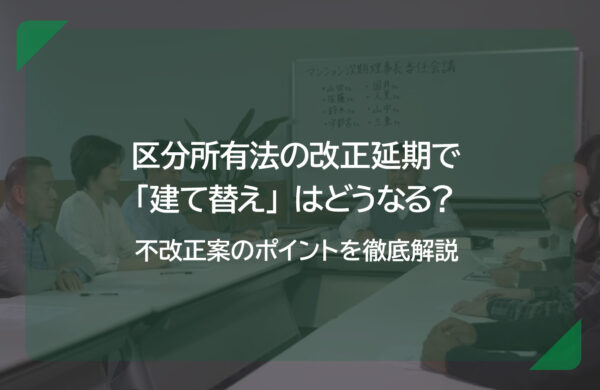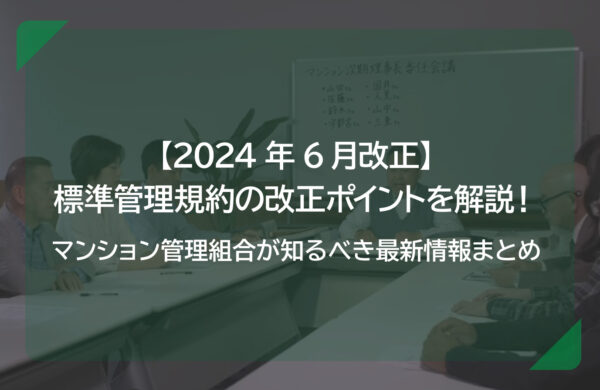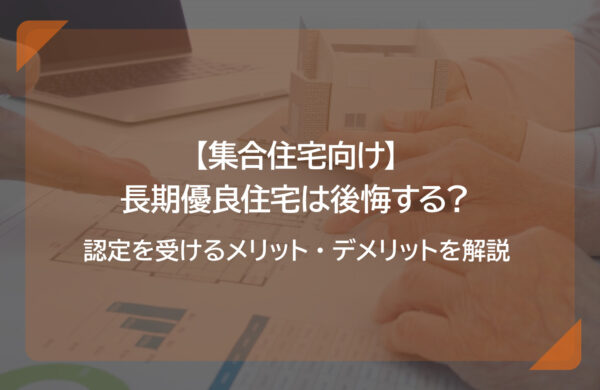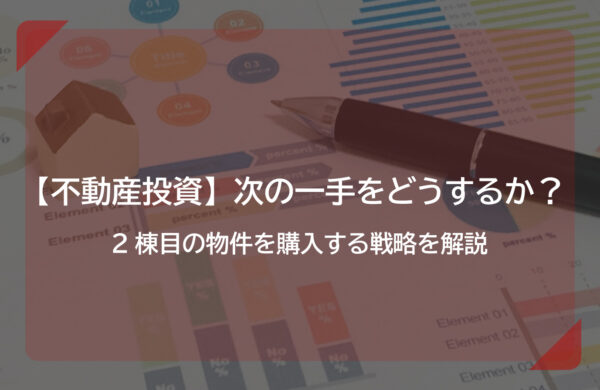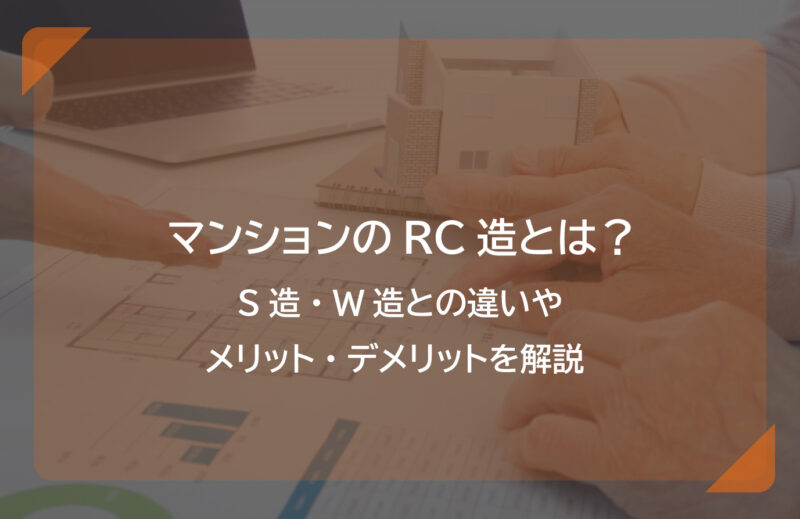
マンションやアパートなどの不動産投資を検討する際、構造に関する知識は欠かせません。建物にはRC造、SRC造、S造、W造といった構造があり、投資目的に合わせて選択するのが重要です。本記事では、それぞれの構造の違いやメリットとデメリットに加え、どのような人がRC造に向いているのかも解説します。
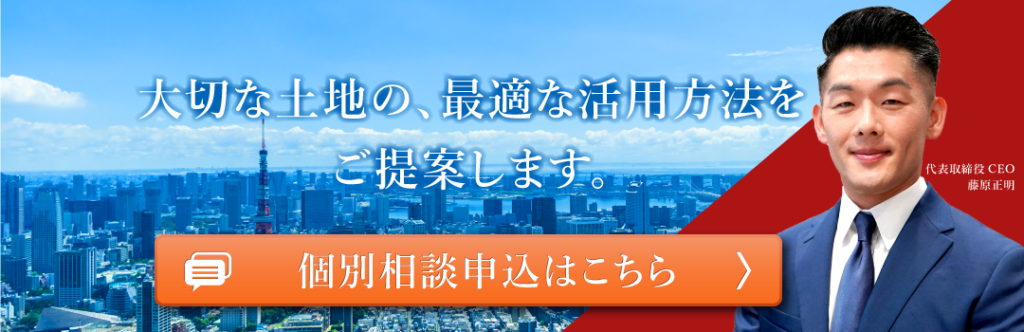

目次
マンションのRC造とは何か
RC造とは、鉄筋コンクリートで建築する工法です。RCは「Reinforced Concrete(補強されたコンクリート)」の略称です。建物の骨組みとなる鉄筋を組み立て、型枠で覆い、コンクリートを流し込んで固めていきます。
鉄筋とコンクリートはそれぞれ逆の特徴があります。鉄筋は引っ張られる力に強い一方、圧縮には弱い特性があり、コンクリートは圧縮に強い半面、引っ張られる力には弱いのが特徴です。
また、鉄筋は酸化すると錆びてしまいますが、鉄筋を覆うコンクリートはアルカリ性が強いためさび錆びの発生を抑える働きが期待できます。熱に弱い鉄筋に対し、コンクリートは防火性が高く、建物としては高い耐火性能を実現できます。このように、鉄筋とコンクリートのそれぞれの特徴を生かして高い強度を実現できるのがRC造です。
RC造のメリット・デメリットを解説
RC造にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。それぞれ詳しく解説します。
RC造のメリット
RC造は、耐火性、耐震性、耐久性、遮音性、断熱性に優れているとともに、比較的自由なデザインが可能であることがメリットに挙げられます。一つずつ解説します。
まず耐火性に優れる点です。コンクリートは火に非常に強く、火災で建物が倒壊する危険性を抑えられるうえ、住戸間の延焼を防ぎ、安全に避難する可能性を高められるでしょう。
耐震性の高さもポイントです。地震発生時、引っ張られる力に強い鉄筋と、反対に圧縮される力に強いコンクリートの長所が組み合わさることで、抵抗力が増して建物の倒壊を防ぎます。全国生コンクリート工業組合連合会によると、1995年の阪神・淡路大震災の際、神戸市灘区でRC造の建物が全壊した割合は約9%でした。5割を超えたW(木)造や2割超のS(鉄骨)造に比べると、被害を抑えられました。
耐久性がある高い点も、RC造のメリットです。コンクリートは木材などに比べて経年劣化が起きにくく、適切なメンテナンスを行えば、長期の利用が可能です。減価償却費を計算する際の法定耐用年数は47年で、S造の19~34年、W造の22年より大幅に長く設定されています。耐用年数が長いと中古物件を売買する際、買い手に融資がつきやすくなる点もメリットになります。
遮音性や断熱性の高さも魅力です。RC造はコンクリートを使うため隙間が少なく気密性が高いのが特徴で、外部や隣室からの音を遮断し、騒音の少ない快適な生活を送れます。断熱性の高さからエアコンを効率良く利用でき、夏は涼しく冬は暖かく過ごすことが可能で、光熱費の節約にもつながるでしょう。
さらに、RC造はデザインの自由度も高いです。コンクリートで強度を確保すれば、柱のない大空間や大きな窓、曲線的な壁なども作れるからです。仕上げの選択肢も豊富で、コンクリート打ちっぱなしやタイル貼りなど、多様なデザインを表現できます。
このように、RC造は長期的に安心して快適に暮らせる住まいの実現が可能であり、マンション投資において魅力的な選択肢の一つといえるでしょう。
RC造のデメリット
一方でRC造には、コストが高い、工期が長い、重量がある、結露やカビが発生しやすい、取り壊しが難しいといったデメリットもあります。
まず、コストが高くつくことです。RC造は、鉄筋工事、型枠工事、コンクリート工事など現場で多くの工程が必要となり、材料費や人件費がかさみます。国土交通省が公表している「地域別・構造別の工事費用表(2023年)」によると、1平方メートル当たりの費用の全国平均は、RC造が27万8,000円となり、木造(17万7,000円)より6割近く高いです。また、RC造は比較的大きな建物で採用されますので、エレベーターや給水ポンプといった設備が必要になることがあり多く、維持や更新にかかるランニングコストが高くなる傾向があります。
工事期間が長くなるのもデメリットです。複雑な作業工程やコンクリートの養生期間などが必要なRC造は、完成まで時間を要し、1フロア当たり1ヶ月程度の工期が必要とされます。基礎工事や内装、仕上げ、外構工事なども並行して進めることから、おおむね「階数×1ヶ月+3ヶ月前後」の工期を要するのが一般的です。
RC造は、W造などより重量があることもデメリットになりえます。地盤の弱い土地では建物の重さによって地盤が緩み、建物が傾いたり倒壊したりするリスクがあるためです。これを避けるため、地盤を強くする工事を行う必要からコストが膨らむ可能性があります。
また、その気密性の高さから、結露やカビが発生しやすい点も注意が必要です。結露は、室内の水蒸気が冷えて水になる現象です。RC造で結露やカビを防ぐには、十分な換気を行う必要があります。
RC造はその堅牢性のため、増改築や取り壊しの費用が高くなるデメリットもあります。
ここまでRC造のデメリットを確認してきましたが、耐震性や耐久性などRC造の持つメリットを踏まえると、長期間でみたときには他の構造より利回りが上回る可能性も十分あります。建物の構造を検討する際には、目先のコストだけでなく、長期間のシミュレーションを行い、判断することが重要です。
他の構造(SRC造・S造・W造)の違いとは
建物の構造には、RC造のほかにSRC造、S造、W造もあります。それぞれの特徴を理解し、RC造との違いを把握することで、最適な構造を選択できます。
SRC造とは
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造は、「Steel Reinforced Concrete」の略称で、鉄骨とRC造を組み合わせた構造です。H形鋼などの鉄骨を支柱とし、その周りに鉄筋と型枠を組み立て、コンクリートを流し込んで施工します。
SRC造のメリットは、耐震性、耐火性、遮音性に優れる点です。鉄には地震などで受けたエネルギーを吸収して耐える粘り強さやしなやかさがあり、他の構造より強度があるため、主に高層建築物に採用されます。コンクリートも使用しているため耐火性も高いほか、鉄骨を入れて強度を確保するのでRC造よりも柱や梁の面積を小さくできるため、部屋を広くすることも可能です。
一方、デメリットとして、建築費が高めになる点が挙げられます。鉄骨と鉄筋コンクリートを併用するため、材料費や工事費がかさみ、分譲価格や賃料も高くなります。国土交通省の「地域別・構造別の工事費用表」で過去3年の1平方メートル当たりの平均工事費用を比べると、SRC造の27万2千円に対し、RC造26万7千円、S造25万9千円、W造17万4千円でした。
支柱に鉄骨を据えるため、RC造やW造などより自由な設計が難しく、工程も多いことから工事期間が長くなる傾向もあります。
SRC造はその強度の高さから比較的大規模な物件に適した構造であり、長期的な資産価値の維持向上を目指す不動産投資家に向いています。初期投資は大きいですが、耐久性と資産価値の高さから、長期的に安定した賃料収入が見込めるのも特徴です。
S造とは
鉄を意味するSteelの頭文字をとったのがS(鉄骨)造です。建物の主要構造部である柱や梁に鉄骨を使用します。鋼材の厚さによって細分類され、6mm未満は「軽量鉄骨造」として主に住居など中小規模に使用され、6mm以上は「重量鉄骨造」として大型施設などによく用いられます。
経済性に優れる点がS造のメリットです。工場で製造された鉄骨を現場で組み立てるため、品質が安定しており、工期も短縮できます。軽量鉄骨を使用することで安めのコストで建設することも可能です。重量鉄骨造は強度があるため自由な間取りを実現でき、大きな空間がある建築にも適しています。軽量鉄骨ならコストを抑えられ、重量鉄骨なら大型物件にも対応できることから、S造は柔軟な工法だといえるでしょう。
一方、デメリットとしては、遮音性と耐火性が比較的高くないことが挙げられます。重量鉄骨造は鉄骨に厚みがあるといっても、壁がコンクリートでできているRC造やSRC造に比べると音が響きやすく、隣室の生活音が気になる方もいるでしょう。鉄は高温の熱で強度が低下し、火災発生時に倒壊するリスクもあります。湿気による錆びを防ぐ防錆処理も検討が必要です。
減価償却費の計算の前提となる法定耐用年数は、47年のRC造やSRC造に比べて短めになっています。鉄骨造の住宅の場合、鉄の厚さが4mm超で34年、3mm超4mm以下で27年、3mm以下で19年です。
W造とは
W(木)造は、Woodの略称で、建物の主要部分である柱や梁、壁に木材を使用する構造です。戸建住宅や低層アパートなどに広く採用されており、建物を柱と梁で支える木造軸組工法(在来工法)や、床や壁で支えるツーバイフォー工法(木造枠組壁工法)があります。
W造のメリットは経済性に優れる点です。他の構造と比べて資材価格を抑えられ、工程がRC造やSRC造に比べると少ないため工期が短いです。構造上小規模な建物が多く、修繕費を抑えられるうえ、固定資産税も比較的低いことからランニングコストを抑えられます。
加えて、木材は調湿性能が高く、湿度の高い日本に適した通気性の良さも利点になります。軽量で地盤への負荷が少ないのもメリットです。二酸化炭素排出量が少なく、温室効果ガス削減に貢献できることから、環境面でも持続可能性が高い工法といえます。
木材は鉄より強度が落ち、RC造などに比べ耐震性が劣るイメージがありますが、軽量でしなやかさがあるため、地震による揺れの作用を逃がしやすくする効果も期待できます。適切に構造計算を行えば、地震に強い住宅を建てることが可能です。
一方、デメリットとしては、品質や性質によるムラが出やすいことが挙げられます。木材の強度は樹種や品質によって異なるほか、職人の施工技術の影響も受けやすいためです。木は腐って形が崩れたり、シロアリなど害虫の被害を受けやすかったりする欠点もあり、適切な維持管理が必要です。
減価償却費を計算する際の法定耐用年数は、22年と短めです。建築から年数が経過し、耐用年数が超過していたり残り少なくなったりしている中古物件の場合、融資に慎重になる金融機関が増えます。このため、出口戦略を検討する際に売り先の候補が狭まる可能性もあります。
RC造マンションを選ぶ人の特徴とは
RC造は、耐火性や耐震性の高さから、火災や地震など災害リスクを懸念する方に人気があります。特に、建物が密集している都心部や地震の多い地域では、安全性と資産価値を維持する観点からRC造を選択する不動産投資家が多いです。騒音や生活音に敏感な入居者から、遮音性の高いRC造が好まれる傾向もあります。
初期投資は高くなるものの、長期的な資産価値の維持と、安定した賃料収入を目指す投資家にとって、RC造は魅力的な選択肢です。
防音性が高いRC造マンションであるか判断する方法とは
RC造マンションは防音性に優れていますが、物件によって差はあります。ここでは、防音性が高いRC造マンションであるかを判断するための方法を紹介します。
方法1:壁を叩く
壁を叩くことで、壁の密度を確認し、隣接する住戸との間の防音性を調べられます。RC造といっても、石膏ボードやグラスウールといった吸音材を組み合わせて壁が造られていると、防音性が低くなることがあります。壁を叩いた際、低く詰まった音がするマンションは、コンクリートの密度が高く、優れた防音性を持っていると判断できます。一方、高く軽い音がするマンションは、密度が低く、防音性が劣ると考えられるでしょう。
方法2:窓を閉めて手を叩く
マンションの防音性を確認するもう一つの方法は、室内で手をたたくことです。窓を閉めた状態で手をたたき、音の反響を確かめます。防音性の高いマンションでは、音が壁に吸収されずに跳ね返ってくるでしょう。この現象は、コンクリートの密度が高く、音の伝達を抑える構造になっていることを示しています。逆に手をたたいたときの反響音が小さいと感じた場合、生活音が外に漏れやすいと考えられます。
ただし、マンションの防音性は構造だけでなく、様々な要因に影響されるものです。間取りや部屋の位置取りも重要で、例えば、居室が共用廊下や階段から離れている場合、生活音は伝わりにくくなります。
方法3:構造を確認する
防音性を調べるには、マンションの構造を確認することも大切です。RC造には、「ラーメン構造」と「壁式構造」という2つがあります。ラーメン構造は、鉄筋コンクリートの柱と梁で建物を支える方式で、一般的なマンションやオフィスビルに採用されます。壁式構造は壁で建物を支える方式です。通常、壁式構造の方が、壁が厚くなるため、防音性能が高いとされています。上下階を区切る床の厚みも防音性に影響します。こうした構造に関する情報は、不動産会社や管理会社に確認するのがおすすめです。
結局、マンションの構造はどれにすべき?
不動産投資では、建物の構造への理解が欠かせません。ここでは、投資目的や立地などに応じたマンション構造の選び方について解説します。
建物の大きさが制限されるならW造
建物の高さが制限される場合はW造がおすすめです。木材は鉄骨やコンクリートより加工が容易なため、柱や梁の調整や形状の変更がしやすく、柔軟な設計に適しています。柱の間隔を調整することなどで限られた空間を有効に活用しやすいのが特徴です。狭小地や高さ制限のある地域での建設に適しています。
土地の条件が合うならRC造
土地の条件が合うなら、長期的に安定した収益を生み出せるRC造の選択が有利です。RC造は建築コストが高いため、部屋数を多めに確保できる規模でなければ採算が合いにくくなります。中高層まで建築できる法令など土地の選定が重要です。
耐震性・耐火性を求めるならSRC造
耐震性と耐火性を最優先とする場合は、SRC造がおすすめです。鉄骨の弱点である耐火性の低さはコンクリートでカバーし、地震の揺れに対しては鉄骨や鉄筋で補強できます。強度があるため、戸数を多く確保できる高層マンションとすることも可能です。
まとめ
マンション投資では、建物の構造を理解し、目的に合った選択をすることが重要です。耐震性や耐火性に優れ、長期的に安定した家賃収入を見込めるRC造は、条件さえ合えば不動産投資家にとって最適な選択となる可能性があります。どの構造を選択するかは、立地や予算、投資目的などによって変わります。RC造を含め、W造、S造、SRC造それぞれの構造のメリットとデメリットを踏まえ、不動産の専門家に相談するのがおすすめです。大和財託では土地の活用についての個別相談を開催しております。建築ありきのご提案ではなく、常にお客様の利益を第一に考えて、長期的に安定した運用を目指すのが、大和財託の土地活用サービスです。